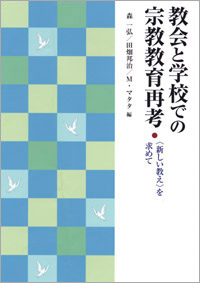��������
|
�I���G���X�E�Z�~�i�[
=�J�ÏI��=��114��
�e�[�}�F�p���X�`�i���Ɠ��{�̐ӔC�F���ێi�@�@�ւɂ��K�U�ɂ�����W�F�m�T�C�h�F��𒆐S��
�u�t�F�������i�����w�@��w���_�����j
�����F2025�N12��11���i�j18�F30�`20�F30
�ꏊ�F�I���G���X�@���������QF �}����
�@17���I�A�O���e�B�E�X�����[���b�p�ł̍��ƊԂ̊W�������@�ijus gentium�j�Ɋ�Â����ՓI�̖@�Ƃ��čl���悤�Ƃ��Ĉȗ��A���ۖ@�ł͌����Ƃ��č��Ƃ͑����ɑ��镐�͍s�g�₻��ɂ��Њd���֎~����Ă���B���ێi�@�ٔ����́A���̍��ۖ@�Ɋ�Â��č��ƊԂ̖@�I����������C���Ƃ��鍑�A�̏�ݎi�@�@�ւƂ��Đݒu���ꂽ�B��A�t���J�͂��̍��ێi�@�ٔ����ɑ��āA2023�N10���̃n�}�X�ɂ��K�U�n��C�X���G����̒n�̃��_���l�ւ̍U���ŊJ�n���ꂽ�p���X�`�i�l�ƃC�X���G���l�̐푈�ɂ��āA�C�X���G���ɂ��W�F�m�T�C�h���ᔽ�ł���ƒ�i�����B�����̓h�C�c�����_���l��g�D�I�ɎE�Q�����z���R�[�X�g���_�@�ɑ�2�����E����Ɍ��ꂽ���̂ł���B�K�U�n��̐l���ɑ��鐢�E�̃��_�����k�ƃL���X�g�҂Ȃǂɂ��Ή�����{�ł̎�����܂߂ĕ���B

�Z�~�i�[�̂��\�����݁E�₢���킹�@
�i�ǂȂ��ł����Q�����������܂��̂œ����܂łɂ��\���݂����肢�������܂��B���^���Ƃ��ăZ�~�i�[���ɂĈ��500�~��\���܂��B�Ȃ��A�Z�~�i�[�I����Ɏ��R�Q���̉��3,000�~�`4,000�~���x�̍��e���\�肵�Ă���܂��j
���I���G���X�E�Z�~�i�[2025�N�x�e�[�}��
�u�Θb�v�\�\���㐢�E�Ə@��
�@����Љ�́A�O���[�o�����ƃf�W�^�����̐i�W�ɂ���āA���l�ȕ����≿�l�ς����������ƂȂ��Ă���B����ŁA�o�ϓI�i���̊g�������̐[�����AAI�Z�p�̔��W�Ȃǂ��V���ȑΗ���f��ݏo���Ă���B���������ɂ����āA�@���͂ǂ̂悤�Ȗ������ʂ����A�Љ�̑��ݗ����ƘA�т𑣐i�ł���̂��B�{�Z�~�i�[�ł́A�u�Θb�v�����ɁA�@��������Љ�Ƃǂ̂悤�Ɍ��������ׂ�����T������B
�@�o�ϓI�E�Љ�I�i���̊g��ɑ��āA�@���͎��P������Љ�`�̐��i��ʂ��āA�l�X�̘A�т��x����d�v�Ȗ������ʂ�������B�ϗ��I���l�ς̍čl���܂߁A�@�����ǂ̂悤�ɎЉ�̈���ƒ��a�Ɋ�^�ł���̂����l�@���A�@���Θb�̋�̓I�Ȏ��H���@��͍����邱�Ƃ́A�����\�ȕ��a�\�z�ɂ����ĕs���ȗv�f�ł���B
�@����ɁA��r�@���̎��_����A�@���̑��l���d���A�قȂ�@���Ԃŋ��L�\�ȗϗ��I�E���_�I��Ղ����o�����Ƃ́A�Θb��[���������ŏd�v�ȉۑ�ƂȂ�B�����āA�C��ϓ�����j�[�������錻��ɂ����āA�@�������u���R�Ƃ̑Θb�ƒ��a�v�̎v�z���ĕ]�����A���ϗ��ւ̍v���̉\����T�邱�Ƃ����߂���B
�@�܂��AAI�Z�p�̔��W���l�Ԃ̉��l�ς�ϗ��ςɗ^����e���ɂ��Ă��l�@����BAI�Ə@���̊W��A�e�N�m���W�[�Ɛl�Ԑ��̖��ȂǁA�@���������̎Љ�ɂ����Ăǂ̂悤�ȈӋ`����������̂���T�邱�Ƃ��K�v�ł���B
�@������������̕ω��ɑΉ����A�J�g���b�N������o�`�J������c�ȍ~�A�u�Θb�v���d������p���ւƓ]�����w�i���ӂ܂��čl�@�������B
�I���G���X�E�Z�~�i�[
=�J�ÏI��=
��113��
�e�[�}�F�Θb�Ɣ�r�\�\�@���ԑΘb�ɂ�����@���w�̖���
�u�t�F�߉���Y�i������w���_�����j
�����F2025�N11��20���i�j18�F30�`20�F30
�ꏊ�F�I���G���X�@���������QF �}����
�@�T�v�F�Θb�͎��ȂƑ��҂��o��Ƃ���Ő�����B���̂Ƃ��A���ȂƑ��ҁi�킽���Ƃ��Ȃ��j���u�����v�ł���_�Ɓu�Ⴄ�v�_���A�Ƃ��ɑO��Ă���B�@���ԑΘb�ł����l���낤�B�@��A�Ə@��B�̑Θb�́A�@A�AB���Ƃ��ɏ@���ł���_�ł́u�����v�����A�A���̓��e�ɂ����āu�Ⴄ�v�A�Ƃ̑z��̂��ƂɂȂ����B�@���w�́A�@���ԑΘb�̑O��ł��邱�̓�̗v���𐬂藧�����Ă���w��I�n�������邱�ƂŁA�Θb�̎��H�Ɏ�����B���������@���w�́A�L���X�g�������@���Əo��A�Θb�����݂邱�ƂŐ��܂ꂽ�̂������B���̍ہA�@���w�́u��r�v�Ƃ����ϓ_������B�@���w���s�����@���̔�r�Ƃ͂ǂ̂悤�ȍ�ƂȂ̂��A���̐��i�ɂ��Ď������q�ׂĂ݂����B
�@�Q�l�}���F�w������Ӗ��@�\�L���X�g���ւ̖₢�����x�@�������V�E�߉���Y�E�K�����ȁE�B�{���� ���@��
=�J�ÏI��=
��112��
�e�[�}�F���@���̐_�w�̑n�n�҃W���b�N�E�f���v�C�ɂ��u���H�I�ȃA�K�v�ɂ���
�u�t�F���������C�_���i���{�J�g���b�N�_�w�@�����j
�����F2025�N10��23���i�j18�F30�`20�F30
�ꏊ�F�I���G���X�@���������QF �}����
�@�C�G�Y�X��i�Ղ̃W���b�N�E�f���v�C�t�i1923�|2004�N�j�̓x���M�[�o�g�̐_�w�҂ł��B�ނ�1948�N����84�N�ɂ�����36�N�Ԃɂ킽��C���h�Ő鋳�t�Ƃ��Ċ��A�C�G�Y�X��_�w�@�̋��`�_�w�����߂�����łȂ��A���ɂ��q���h�D�[���╧���̍���ɐ��ޏ@�����̌�����L���X�g���Ə��@���̔�r�����ɂ��͂�s�����܂����B���̌�A���[�}�ɏ�����ăO���S���A����w�ŋ��`�_�w���b�_�w�̋��ڂ����邩�����A���Ђ���_�w����̊w�p���w�O���S���A�[�k���x���̕ҏW�������߂܂����B�ނ́u���@���̐_�w�v�̑�ƂƂ��Ē����ł����A���Ƃ��Ƃ͋��`�_�w�i�~�Ϙ_�A�L���X�g�_�j�⋳���v�z�̐��Ƃł����B�ނ����߂����@���̐_�w�̍ŏI�I�Ȍ��_�́u�A�K�y�i�_�̎����j�ɂ���Ĕ��肷�邱�Ƃ̏d�v���v�ł����B�����ɐ^�������߂ďC����ςݏd�˂�@���҂�c�̂͐����Ȑ������ɂ����āA���̂�����A�K�y���������܂��B�f���v�C�t���ˋ�����Ñ㋳���̔��z�ł́A���������l�Ԃł��邱�Ƃ��̂��̂ɂ����Ă��łɐ_�̎q�Ƃ��Ă̎��i������_�̎��p�ւƐ��n����\�����߂Ă���̂ŁA�l�Ԃ͐_�̎����������ł��܂��B���H�I�Ȉ����L���X�g�����������܂��B
�@�Q�l�}���F�w�L���X�g�ƂƂ��Ɂ\�\���E���L����_�w����x�@���������C ���@��
=�J�ÏI��=
��111��
�e�[�}�F�\���Ƃ��Ă̐V�g�}�X�E�V�X�R���w�\�\�ߌ�����{�ł̉��W�̌`���j�������Ɩ{���ւ̓����i�e�[�}�C���j
�u�t�F���Z �^�搶�i������w���_�����j
�����F2025�N9��25���i�j18�F30�`20�F30
�ꏊ�F�I���G���X�@���������QF �}���� (���L�n�})
�@�L���X�g���̋����܂��J�g���b�N�̉��ߌ���łǂ̂悤�Ȉʒu��e�������������B
���܂�m���Ă��Ȃ����d�v�Ȏv�z�Ƃ�H��A���̓��{�ł̎d�g�݂�H��B�܂������E���̂̓��e�����o���≺�s��̍l���̓W�J���݂Ă��̓V�c�Ƃ̊W���m��B�܂��ߌ���̎Y�Ƃ̊ԈႢ���Ƃ炦�_�Ƃ��������𗬁E�`���̉��c���l��W�_�҂�m��B�X�ɉ╽�a��m������O�̏�c�C�V���A���̉F��O���̌o�Ϙ_������B�Ō�ɁA���݊������̃e���[�E�C�[�O���g���̕����_���A����ԈႢ�𑨂��Ȃ���̉ւ̉��ɂ��Ȃ�B���A�����ɂ���͉̂��Ȃ̂��A�A�K�y�i���j�̂��Ƃł͂Ȃ����B�ڍׂł͂Ȃ��v�_���Ƃ炦�Ȃ��猻�݂ւ̕��������o�������B
�Q�l�}��
�@�����w�����鋳�x2025�N6�����A8�E9�����A10�����ł́A�����a�Ɓi���S���q��w�����j���u�≺�s��̐t�v�Ƒ肵���D�]�A�ڂ��f�ڂ��Ă���܂��B
�@�\�\�吳���ォ���O�ɂ����ē��{�̃J�g���b�N����̎i�ՂƂ��āA�܂��N�w�ҁA����҂Ƃ��Ă����łȂ��A����ɏo�ł╟���Ȃǂ̎Љ�Ƃ��܂ޑ����ʂ̊����ɏ]�������≺�s��i�ꔪ����]���l�Z�j�́A�c�O�Ȃ��ƂɌ��݂ł̓J�g���b�N����̒��ł��\���ɒm��ꂽ���݂ł͂Ȃ��B��Z�N�ȏ�O�ɁA����S�������ނ����グ���Ƃ��Ɂu�w�Y���ꂽ�v�z�Ɓx�ƌĂꂽ���Ƃ���Y����Ă���v�Ə��������Ƃ����邪�A���͂���ɖY�p�̔ޕ��ɂ���Ƃ����Ă悢���낤�B�M�҂������N�w�������u�������A�≺�����N�w�Ȃ̏G�˂Ƃ��ď��������]����A�����N�w�u�����J�݂��邱�Ƃ����҂��ꂽ�̂ɁA�i�ՂɂȂ��Ă��܂������߂Ɏ������Ȃ��������Ƃ�m�����B���ʂƂ��āA���Ɏ���܂œ�����w�ɂ͒����N�w�̍u�����u����Ă��Ȃ����Ƃ����݂Ɏv�������̂́A����ȏ�̊S�͎����Ȃ������B�Ƃ��낪�ߔN�A�l�X�ȉ��ƕs�v�c�ȏo��ɓ������܂܁A���̖Y���ꂽ�l���̎��тɐg�߂ɂӂ�邱�ƂƂȂ����B���́A�≺�s��́A�����ȍ~�̓��{�ɂ����čł���z�����L���X�g�҂̈�l�ł���A�܁Z�N�̒Z�����U�Ȃ���A�[���w���ƕ��L�����{����������o�����m���l�ł���ƂƂ��ɁA�S���͂𒍂��Ŏ�҂�a�҂̂��߂Ɍ��g�����D�ꂽ���H�Ƃł����������Ƃ��m�M���Ă���B�i�����w�����鋳�x2025�N6�����u�≺�s��̐t�i1�j�v���j
�@���d�q��note �����w�����鋳�x�̊e�f�ڋL���́A�P�̂̋L���i100�~�j�Ƃ��Ă������߂ɂȂ�܂��B
���≺�s��̐t�i�P)�@�≺�s���n�������́\�\���E�R�{�M���Y�E�P�[�x���@(�����w�����鋳�x2025�N6�����f��)
���≺�s��̐t�i�Q)�@�������܂܂Ɂ@(�����w�����鋳�x2025�N8�E9�����f��)
���≺�s��̐t�i�R)�@20���I�̃t�����V�X�R�E�U�r�G���@(�����w�����鋳�x2025�N10�����f��)
=�J�ÏI��=
��110��
�e�[�}�F�������[���b�p�̐g�́\�\���ƃ_���X�̊ϓ_����
�u�t�F�㓡���ؐ搶�i�R�w�@��w ���w���j�w�ȏy�����j
�����F2025�N7��18���i���j18�F30�`20�F30
�ꏊ�F�I���G���X�@���������QF �}����
�@�����_���X���A�������[���b�p�ł́A���ꂪ�l�Ԃ̐S�g������������̂ł��邪�䂦�ɁA������߂ƌ��т����A�����ے�I�ȕ������J��Ԃ��o����Ă����B�������ɂ͎��̕����Ƃ����\�ۂ��m���Ă���B�������A�폟�Ȃǂ̏j�����̋V��ɂ�����x��͌Ñォ��s��ꑱ���Ă���A�{��Ƃ�����Ԃ���ɂ�āA�_���X��l���킹��C�̗������f�{�́A�M���E�R�m�̚n�݂ƂȂ����B�ނ��_���]���邽�߂ɓV�g��l�������g�𓊂���̂�_���X�́A�ǂ����́A�K�v�Ȃ��̂Ƃ��Č���Ă����B
�@�{���\�ł́A�����Љ�ő��l�ȉ��l�ς����������������ƃ_���X�ɏœ_�Ă邱�Ƃɂ���āA���̑o���Ɗւ��u�g�́v�ɂ��Ė₢�����A�Θb����@��Ƃ������B
�@�Q�l�}���F�w���ق̒����j�\�\����j���猩�郈�[���b�p�x�@�㓡���ؒ��i�����ܐV���j
=�J�ÏI��=
��109��
�e�[�}�F�@���ԑΘb�̕K�v���Ɖ\���\�\�L���X�g���Ə��@���ɑ�����o�`�J������c�̐錾�A60���N
�u�t�F�J�u���f�B�E�I�m���i�J�g���b�N�~�S��i�ՁA�I���G���X�@�������������j
�����F6��27���i���j18�F30�`20�F30
�ꏊ�F�I���G���X�@���������QF �}����
�@����̃J�g���b�N����̕��������߂��A���o�`�J������c�i1962�]65�N�j�ł́u�L���X�g���ȊO�̏��@���ɑ��鋳��̑ԓx�ɂ��Ă̐錾�v�����\����Ă���A���N��60�N���}���܂��B
�@������L�O���A���@���ɑ���L���X�g���i�J�g���b�N����j�̑ԓx�A�@���ԑΘb�̕K�v���Ɖ\���ɂ��ĕ��͂��A�L���X�g�҂̐M����_�̋~���͏@���̋��E���z����̂��ɂ��āA�@��������`�Ƃ̊W�A�_�̌v��̒��ł̏��@���̈ʒu�Â����������A�����̏@�������ї��A�t���J�ł̌o������@���ԑΘb�ւ̐V���Ȏ��g�݂���܂����B
�@�Q�l�}���F�w���E���z����_�̋~���̌v�� ���@���ԑΘb�̐V���Ȓn���ցx�@�J�u���f�B�E�I�m����
=�J�ÏI��=
��108��
�e�[�}�F�u�Θb����v�Ɍ����ā\�\�g�}�X�E�A�N�B�i�X����w��
�u�t�F�K�����Ȑ搶�i�}�g��w���_�����A���{�J�g���b�N�_�w�@�u�t�j
�����F2025�N5��16���i���j18�F30�`20�F30
�ꏊ�F�I���G���X�@���������QF�}����
���J���i��t�I���j��
�w�I���G���X�E�Z�~�i�[�x2025�N�@���N���ʊ��
�e�[�}�@���N����݁A�����邽�߂Ɂ\�t�@�V���e�[�V�����̕��@���w�ԁ\
��ÁF�I���G���X�@���������@�@���́F�J�g���b�N������i����
�ꏊ�F�J�g���b�N��������@���� �@��156-0043�@�����s���c�J�揼��2-28-5
�i�������E��̓����u����O�w�v���k���T���j
�����E�u�t�E���F���L�����Q�Ɓ^�e��14���`17���E���Q���̂ݑS7��i8���x�u�j�E6,600�~�i�ō��j
5/17�i�y�j�A6/21�i�y�j�A7/19�i�y�j�A9/6�i�y�j�A10/�S�i�y�j�A11/15�i�y�j�A12/6�i�y�j
�e�[�}�i��|�j�F
���N����]�������ĕ��ނɂ��߂ɁA�J�g���b�N������i����̋��͂̂��ƁA��16��ʏ�V�m�h�X�ōs��ꂽ�u��ɂ������b�v�̐i�ߕ��𒆐S�ɁA���̗v�ƂȂ�t�@�V���e�[�V�����̎��H���@���w�сA�g�ɂ���v���O�������J�Â������܂��B
�������ڍׂ͂����炩�炲�Q�Ƃ��������B������
��2002�N����n�܂����I���G���X�E�Z�~�i�[�i����������j�́A�����f����ꂽ�����e�[�}�u�M�̖ڂ������Ă���ߑ���{���_�j�̏����̌����v�ȗ��A�����܂ŁA��Ƃ��ē��{�ɂ�����L���X�g���̂��肩�����߂����Ď�X�̉ۑ���������Ă��܂����B
���I���G���X�E�Z�~�i�[2018�`2020�N�x�̃e�[�}��
�u����Љ�ɂ�����`���̐V���Ȗ����v
�@�l�Ԃ͗��j��ςݏd�˂Ă������A���K���ɂȂ邽�߂ɁA�Ȋw�Z�p�W�����Ă����B�������Ȃ���A�i�s����IT�i���Z�p�j�̔��W�́A�������ɍK�������炷����ł͂Ȃ��A�����̐l�X������Ɏx�z����Ă���Ƃ������ʂ��o���������B�Љ����̋}���ȕω��A�ɓx�̌l��`�A�l�Ԃ̊W���̊���ϖe�Ȃǂɂ���āA�l���̉��l���h�炬��@�ɕm���Ă���Ƃ��������悤�B���̉e���͎Љ���̂����鑤�ʂɋy��ł���B�ŋ߁A����IT�𒆐S�Ƃ��鐢�E�͂��������u���z�����Ȃ̂��H�v�Ǝv����悤�ȁA���������f�W�^��������l�Ԃ����グ�悤�Ƃ���u�|�X�g�q���[�}���v�v�z�ɂ܂œW�J���Ă���悤�ł���B�������A�l���ɂ����Ă̈��S���≿�l�ς̊���A�@���E�����E�i�i�ɂ��̂ł͂Ȃ��A�����I�ȓ��v�f�[�^�ɂ���Ē�߂���悤�ɂȂ�����������B
�@���̂悤�Ȑl�Ԃ̑��݂�Љ�̏��������������Ƃ��Ă��铮���Ɏ��~�߂������悤�Ƃ���l�X������Ă��Ă���B�ނ�́A��`�q�g�݊����앨�������D�悳����o�ς�ے肵�A�l���̍����I�Ȗ₢���l���Ă���B���E�̏��������ω����钆�A�@����`���ɏd����u�������l�ɂ����d����ׂ����̂�����ƍl���A������������̊�@�ւ̔F������o�����A�Ȋw�Z�p�̂����炷�����̊g��Ƃ��̉\���𗘗p���A�������сE�K���Ȑl�������o�����߂ɁA���l�ς̑��l���Ǝ���̕ω��ւ̑Ή����l�@���Ă݂����B
�@���ẮA2016-17�N�̓��Z�~�i�[�ɂ�����u��������ʂ��ē����сv�Ƃ����e�[�}�Ɉ��������A2018�N���A���c�t�����V�X�R�̎g�k�I�����w���̂�낱�сx�ɂ����Ď��グ���Ă���Ƒ��E�ƒ�̏���������ɓ���Ȃ���A���悢�Љ�̘A�ѐ��Ɛl�Ԃ��J�����߂��@���A�`���̐V���Ȗ�����T���Ă����B
���ߋ��̊J�Ãe�[�}���i��E���͓����j
�@�@
�u�I���G���X�E�Z�~�i�[�v�̔��\�E�������܂Ƃ߂�����