月刊 福音宣教
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
2023年 年間テーマ:かけがえのないいのちに出会う バックナンバー (著者・記事一覧)
1月号 2月号 3月号 4月号 5月号 6月号 7月号 8・9月号 10月号 11月号 12月号
○月刊『福音宣教』トップページ
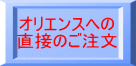
○富士山マガジンサービスからご注文
時代を超えた大切な信仰の光 コンスタンチノ・コンニ・カランバ
◆憲法とキリスト教 第1回 なぜ法学は宗教思想から距離を置くのか 南野 森×森島 豊×久保文彦
日本国憲法の中心である個人の尊厳とキリスト教は、明らかに関係があるようにみえますが、なぜそのことがあまり語られてこなかったのか。王権と教会との結び付き、宗教対立の時代背景など、近代立憲主義の成り立ちを南野先生がわかりやすく解説。
◆約束の地への旅、楽園への帰還 濱田欧太郎
◆本当のチーム、共同体とは――コロナ禍の世界で見えたことを通じて 赤井悠蔵
共同体ではない教会はなく、共同宣教司牧でない司牧はない。生活支援もまた立派なチーム・ミニストリー〈共同宣教司牧〉であることなど、今の教会に一番必要な精神が語られています。
◆インタビュー 間野正孝師――旭川市内のチーム・ミニストリー 編集部
司祭が高齢化し減少していく中で、地方の教会はどのような変容を迫られているか。カトリック札幌教区旭川地区から、具体的な事例がレポートされます。
◆東京教区カテキスタ、発足から四年目 編集部
担当司祭である猪熊師や、実際のカテキスタである本誌編集担当鈴木から、東京教区のカテキスタたちがどのように活動し、いかなる問題に直面しているか、具体的に語られます。
◆京・江戸・博多、そして巴里 12 カルメル山登攀 南野 森
◆祈りがないと生きていけない 第1回 祈りとの出会い 萩原千加子
◆使徒的書簡 Desiderio desideravi(切に願っていた)を読む
――教会活動の頂点であり源泉である典礼について 第1回
書簡の動機――教会一致の視点から見た典礼 フランコ・ソットコルノラ
◆栗田隆子と、フェミニスト神学に学んでみよう! 第1回 フェミニズムとは? 栗田隆子
◆イエスのたとえ――生きる希望のしるべとして 第1回 「種を蒔く人」「成長する種」のたとえ 本多峰子
◆私とイエスとの出会い 第1回 人に最も必要なもの 今村勝己
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語 第1回 「ヘブライ語」という遺産 高橋洋成
◆つうしん
note(電子版)による記事購入↓

◆憲法とキリスト教 第2回 聖書と憲法の共通点 南野 森×森島 豊×久保文彦
法実証主義に基づく実定法は、悪法でも違法ではない可能性があり、ナチズムにも利用されたため、その反省から戦後ドイツでは自然法の復権がありました。人間らしく生きるための参考書でもある聖書と日本国憲法の共通点とは。
◆「シノドス的教会を目指すカトリック教会」のコミュニオン――大陸ステージのための作業文書をどう読むか 原 敬子
今期シノドスの「回心と改革の旅」のために、全世界から集められた回答書では、どのようなことが考えられ、何が目指されているのか。宣教するシノドス的な教会となるための取り組みを解説。
◆東北地区でのカトリック学校教員養成 土倉 相
宗教教育をすることが難しくなっていく環境の中、「カトリック学校の教職員のための養成塾」などで、長年地道に行われてきた教員同士の分かち合いや仲間作りについて知ることができます。
◆北海道カトリック学園のあゆみ 品田典子
カトリック学校の法人移管の経緯、地域の人口減少やコロナ禍、共学化への準備など、ミッションスクールにとっても厳しい時代の背景と展望について貴重な証言が語られます。
◆函館ラ・サールミッション部とカトリック函館地区青年交流会 韓 徳
札幌教区の湯川教会では、ベトナム人技能実習生への食糧支援が行われています。その活動を通して交流する函館ラ・サールミッション部。信者ではない学生たちの姿は、若者が減った現代日本の教会の希望となる成功例です。
◆風よ! 炎よ! 私にことばを! 18 聖書の当時と今 小林 剛
◆京・江戸・博多、そして巴里 13 いも九、いざ江戸へ 南野 森
◆祈りがないと生きていけない 第2回 神を知る道 佐無田 靖
◆使徒的書簡 Desiderio desideravi(切に願っていた)を読む
――教会活動の頂点であり源泉である典礼について 第2回 典礼はキリストとの出会い――書簡の意図について フランコ・ソットコルノラ
◆栗田隆子と、フェミニスト神学に学んでみよう! 第2回 耳を傾けない罪――メアリー・デイリー『教会と第二の性』を読む 栗田隆子
◆イエスのたとえ――生きる希望のしるべとして 第2回 「ぶどう園と農夫」のたとえ 本多峰子
◆私とイエスとの出会い 第2回 私の信仰体験 赤木啓子
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語 第2回 「神の言葉」という知恵 高橋洋成
◆つうしん
◆憲法とキリスト教 第3回 人間を生かす力とは本当は何か 南野 森×森島 豊×久保文彦
人権思想は一般に近代から始まるという通念がありますが、日本国憲法の中心にもある人権思想の源は、すでに明確に「出エジプト記」や「申命記」など、聖書の中に見いだされることが語られています。
◆教会と学校との「懸け橋」として――教区司祭がチャプレンとして働くことの意義 鈴木 真
◆インタビュー 小田原教会・福祉部――地域のつなぎ役となっている教会 編集部
この教会の福祉活動は、もともとは信徒が個人や数名で地域に出ていき、粘り強く奉仕していたことが始まりです。これらの支援を教会が背後からサポートするようになり、結果的に地域のパイプ役になっていきます。教会が地域社会の中に溶け込んでいる姿に学びましょう。
◆インタビュー 大和教会・社会活動部 編集部
1980年代からボートピープルの難民を支援し、外国籍の人々を受け入れ支えてきた教会の信者たち。その支援は今も続き、このコロナ禍で真っ先に労働力から外され、明日食べるものにも事欠くような方々を大勢支えています。また、奉献生活者のサポートのもと、情報・教育格差に苦しむ子どもたちの学習支援を学生たちが行っている姿をお伝えします。
◆風よ! 炎よ! 私にことばを! 19 シノドスで迷子? 有村浩一
◆京・江戸・博多、そして巴里 14 教師のやる気、学生のやる気 南野 森
◆祈りがないと生きていけない 第3回 イエスと共に歩む道 佐無田 靖
◆使徒的書簡 Desiderio desideravi(切に願っていた)を読む
――教会活動の頂点であり源泉である典礼について 第3回
神と出会う典礼の中心に――驚き、喜び、感謝! フランコ・ソットコルノラ
◆栗田隆子と、フェミニスト神学に学んでみよう! 第3回
E・S・フィオレンツァ『彼女を記念して』を読む――ないことにされた女性の言葉を刻む 栗田隆子
◆イエスのたとえ――生きる希望のしるべとして 第3回 「善いサマリア人」のたとえ 本多峰子
◆私とイエスとの出会い 第3回 行動する中でイエスと出会い続ける 酒井育子
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語 第3回 「一つの言葉」という混乱 高橋洋成
◆この一冊 坂口ふみ著『〈個〉の誕生――キリスト教教理をつくった人びと』 編集部
◆つうしん
◆憲法とキリスト教 第4回 人権思想と聖書 南野 森×森島 豊×久保文彦
人権思想の裏に聖書があると言った場合、たとえば聖書の中で奴隷制が「認められている」ことをどう考えるのか。聖書の読み方にヒントが与えられます。
◆「こうのとりのゆりかご」の相談室長の蓮田真琴さん 聞き手・黒川京子
「赤ちゃんポスト」が設立された経緯、海外の状況、現在の具体的な運用などについて、現責任者から直接お話を伺っています。
先日逝去したベネディクト16世の若き神学者時代から、教皇となるに至るまでの変遷、他教派・他宗教とのかかわりなどについて、第一線の研究者が分かりやすく教えてくれています。
◆教皇ベネディクトゥス16世の世界史的役割 今野 元
◆教皇ベネディクト16世の帰天に寄せて 松本佐保
◆風よ! 炎よ! 私にことばを! 20 善きサマリア人の猫 鈴木敦詞
◆京・江戸・博多、そして巴里 15 憲法とはどのようなものか 南野 森
◆祈りがないと生きていけない 第4回 識別のいのり 原 敬子
◆使徒的書簡 Desiderio desideravi(切に願っていた)を読む
――教会活動の頂点であり源泉である典礼について 第4回
典礼は過越の神秘の宴、体験 フランコ・ソットコルノラ
◆栗田隆子と、フェミニスト神学に学んでみよう! 第4回 ローズマリー・R・リューサー
『性差別と神の語りかけ』を読む――女性が「自己を空しく」するとは何か? 栗田隆子
◆エッセイ 言葉や口先だけではなく、行いをもって…… 栗田隆子
◆イエスのたとえ――生きる希望のしるべとして 第4回 「仲間を赦さない家来」のたとえ 本多峰子
◆私とイエスとの出会い 第4回 昔も、今も、これからも共に歩んでくれる神様と 川島瑠里子
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語 第4回 「ベニヤミン」という希望 高橋洋成
◆つうしん
◆憲法とキリスト教 第5回 憲法における内面の自由とは何か 南野 森×森島 豊×久保文彦×小林 剛
日本国憲法の中で最も重要な第13条で、尊重されなければならないとされている「個人」とは、一体何か。憲法学者南野先生が分かりやすく教えてくれます。
◆『証し――日本のキリスト者』著者 最相葉月さんインタビュー 編集部
キリスト者150名以上に密着取材し、6年がかりで完成された日本全国のキリスト者の「証し」を集めたこれまで類例のないノンフィクション作家へのインタビューです。諸宗派の異なった感じ方を内側、また外側から垣間見ることができます。
◆インタビュー 大野高志さん 編集部
緩和ケア病棟で、これまで出会い、また別れていった大勢の人々の声の力に支えられて働く大野牧師の姿に学ぶことができます。
◆インタビュー 漆原めぐみさん 編集部
社会から疎外された人々に寄り添う日々から、看取る日々へ、医療ソーシャルワーカーとしての召命にいたるまでにどのような導きがあったのか、分かち合ってくださいました。
◆病者の傍らで 中尾実紀子
長崎県五島で医師として多くの人の生き死ににかかわるシスター中尾の姿に、路上の人にイエスを見たマザー・テレサの姿が重なります。
◆風よ! 炎よ! 私にことばを! 21 筒井哲郎さんの思い出 久保文彦
◆京・江戸・博多、そして巴里 16 憲法とはどのようなものか・続 南野 森
◆祈りがないと生きていけない 第5回 愛と知恵の体験 片柳弘史
◆使徒的書簡 Desiderio desideravi(切に願っていた)を読む
――教会活動の頂点であり源泉である典礼について 第5回
典礼において、人間の聖化が感覚的なしるしによって示され、実現される フランコ・ソットコルノラ
◆栗田隆子と、フェミニスト神学に学んでみよう! 第5回 堀江有里
『「レズビアン」という生き方』を読む――誰が何と言おうとわたしはいま、ここにいる 栗田隆子
◆イエスのたとえ――生きる希望のしるべとして 第5回
「放蕩息子」のたとえ、「見失った羊」のたとえ、「無くした銀貨」のたとえ 本多峰子
◆私とイエスとの出会い 第5回 私と神さまとのつながり 髙木聖美
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語 第5回 「シボレト」という連帯 高橋洋成 高橋洋成
◆つうしん
◆憲法とキリスト教 第6回 天皇型人権 南野 森×森島 豊×久保文彦×小林 剛
戦前から日本で使われ定着していた「人権」という言葉の意味が、いかに戦後の日本国憲法が語る人権と異なっていたか、衝撃を受けます。それは今も現代日本の人権に関する偏った考え方の水面下に依然、存在し、影響し続けているのかもしれません。
◆開かれた部屋と閉ざされた部屋 濱田欧太郎
◆インタビュー 命の心配をせずに暮らしたいだけ――ミャンマーから家族の声 安田菜津紀
運命に翻弄されミャンマーから日本へ逃亡せざるを得ず、いまも苦しみの中でたくましく生きる家族の苦闘の歴史が浮き彫りになっています。現代日本に移動・移住する人々にとって、自由と人権の理不尽かつ暴力的な制限がどのくらい重く課せられているのか、実感できる内容です。
◆インタビュー ベトナムからの人々を支援する 編集部
――ペトロマリア・グェン・フ―・ヒェン神父
――シスター・マリア・レ・ティ・ラン
――ヨセフ・グエン・タン・ニャー神父
ボートピープルを40年以上支援し続けるベトナム人司祭。また、元ボートピープルであり、今はベトナム人のあらゆる相談を受ける専門職であるシスター。そして、日本の小教区の助任司祭であり、わたしたちの教会のために働きながら、空いている時間をベトナム人司牧に捧げている司祭。それぞれが相互に支え合いながら共に支援活動をしている実際の様子を知ることができます。
◆風よ! 炎よ! 私にことばを! 22 どうする地方の教会 伊能哲大
◆京・江戸・博多、そして巴里 17 憲法とはどのようなものか・完 南野 森
◆祈りがないと生きていけない 第6回 サダナ黙想の指導をしながら(1) 植栗 彌
◆使徒的書簡 Desiderio desideravi(切に願っていた)を読む
――教会活動の頂点であり源泉である典礼について 第6回
活きた典礼のための養成――典礼の養成はシンボル(象徴)を理解することから始まる フランコ・ソットコルノラ
◆栗田隆子と、フェミニスト神学に学んでみよう! 第6回 グスタボ・グティエレス
『解放の神学』を読む――フェミニスト神学のベースに流れるもの 栗田隆子
◆イエスのたとえ――生きる希望のしるべとして 第6回
「タラントン」のたとえと「ムナ」のたとえ 本多峰子
◆私とイエスとの出会い 第6回 福音書のつづき 橘 依理子
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語 第6回 「アシュタロト」という緩み 高橋洋成
◆つうしん
◆憲法とキリスト教 第7回 信仰者の心に培われた“権理”意識 南野 森×森島 豊×久保文彦×小林 剛
日本の歴史を振り返り、人権意識や抵抗権はキリスト者の信仰によって培われたという否定しがたい面が指摘されています。この人権意識、抵抗権が、日本でどのように為政者によって危険視され弾圧され、日本国家建設のために歪んだものとなり、その歪みが今に至る矛盾の背景となっていったのかが語られます。
◆これまでのシノドスの歩みとアジアシノドス体験記――「聞く」ことの大切さ 西村桃子
◆政府の原発回帰政策の問題点 松久保 肇
政府の原発回帰政策の根本的な矛盾と問題点を、日本で最も詳しい専門家の一人が総合的に分析。原発は非常に高額なコストのかかる不合理かつ危険で安定性のない技術。日本の原発メーカーも、技術維持のための海外での建設誘致にことごとく失敗。メーカー側の資金ではその高額な費用が捻出できず、税金である国家予算を投与しようとしています。電気代の高騰にも直接つながる非常に問題視すべき事態です。
◆原発政策大転換の愚か 内藤新吾
今回の政策転換の政府の隠れた意図を内藤師が指摘する内容になっています。政府は脱炭素への世界の世論を隠れ蓑に、安全な耐用年数を超えた原発の危険な延長使用を目立たないよう巧妙に進め、核兵器使製造を目的とするとしか見えない燃料サイクルの計画を告発する内容となっています。今こそキリスト者は声あげるべき時です。
※お詫びと訂正 31頁の訂正箇所
◆自分からはじめるエネルギー転換 木村護郎クリストフ
ドイツの原発政策を追ってきた木村氏から、ご自身の家庭で実践している、個人の自宅の脱炭素化の例を紹介していただきました。勇気と知恵の与えられる報告です。
◆風よ! 炎よ! 私にことばを! 23 読者交流会へのお誘い 小林 剛
◆京・江戸・博多、そして巴里 18 憲法に緊急事態条項は必要か 南野 森
◆祈りがないと生きていけない 第7回 サダナ黙想の指導をしながら(2) 植栗 彌
◆使徒的書簡 Desiderio desideravi(切に願っていた)を読む
――教会活動の頂点であり源泉である典礼について 第7回
典礼におけるしるし――シンボルと典礼「文化内化」 フランコ・ソットコルノラ
◆栗田隆子と、フェミニスト神学に学んでみよう! 第7回 マルセラ・アルトハウス=リード
『下品な神学 Indecent Theology』を読む――聖書をクィア(ヘンダイ)として解釈すること 栗田隆子
◆イエスのたとえ――生きる希望のしるべとして 第7回 「不正な管理人」のたとえ 本多峰子
◆私とイエスとの出会い 第7回 神様との出会い 村山雅哉
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語 第7回 「ライオン」という謎かけ 高橋洋成
◆つうしん
◆憲法とキリスト教 第8回 「イエス・キリスト」を語れる人は誰か 南野 森×森島 豊×久保文彦×小林 剛
◆新司教に聞く――(1)大分教区、森山信三師/(2)仙台教区、E・ガクタン師 編集部
月間テーマ 世界各地域のシノドスの動向
ドイツ司教団が、教会の大幅な改革を目指し、性虐待問題を受けての聖職者至上主義の根絶、教会統治の全レベルでの女性参画、同性カップルの祝福などを求める決然とした姿勢を示す一方、教皇庁がブレーキをかける構図。改革を拒絶する勢力との内部分裂、霊的対話が維持できるかが焦点です。
◆フランス教区ステージと欧州大陸ステージ 三浦ふみ
教会は「もっとも小さな声」である、もっとも疎外されている人々の声、差別されている人々の声、また「地球の叫び」を聴くことが欠落していたと強調。シノダリティは、彼らの声に耳を傾けるという実践なしには、変容はないと指摘しています。
◆インタビュー キハーノ司教(ペルー)に聞く 聞き手・山野内倫昭司教
ラテンアメリカとカリブ海諸国では、教会における女性の主体性が欠如する構造に目を向け、性虐待への取り組みの強化、先住民族やアマゾンの自然と移住移動者と難民への配慮について意識を高める必要性も課題に。シノドスの障害に聖職者至上主義を挙げています。
◆インタビュー 李尙潤師(韓国)に聞く 編集部
韓国の教会ではシノドスのために、SNSを活用し、用意周到な聞き取りを行って徹底的な調査を実施。聖職者の権威主義による傾聴の欠落、勇気ある発言のなさ、青少年の意見を聞かず疎外し、司祭だけでなく全員の共同責任という認識不足、社会との対話の不足を挙げ、識別のための養成の必要性を宣言しました。
◆風よ! 炎よ! 私にことばを! 24 大人こそ『こじか』 萩原千加子
◆京・江戸・博多、そして巴里 19 衆議院解散権は首相の伝家の宝刀か 南野 森
◆祈りがないと生きていけない 第第8回 真命山での生活 三谷博子
◆使徒的書簡 Desiderio desideravi(切に願っていた)を読む
――教会活動の頂点であり源泉である典礼について 第8回
典礼を生きるために必要な養成と方法 フランコ・ソットコルノラ
◆栗田隆子と、フェミニスト神学に学んでみよう! 第8回
『日本におけるキリスト教フェミニスト運動史』を読む 栗田隆子
◆イエスのたとえ――生きる希望のしるべとして 第8回 ファリサイ派の人と徴税人」のたとえ 本多峰子
◆私とイエスとの出会い 第8回 さりげない言葉、関わりから 梅木明代
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語 第8回 「アラム語」という文明 高橋洋成
◆つうしん
◆憲法とキリスト教 第9回 カルトとは何か――(1)自分で考えさせない共同体 南野 森×森島 豊×久保文彦×小林 剛
カルト化は宗教だけではなく、あらゆる団体において起きうるという重要な指摘がなされています。社会一般にカルト的なものが蔓延していないか、今一度考え直すために役立つ、貴重な話し合いになっています。
◆シノドスとディアコニア――(1)聖ラウレンチオネットワークのルルド巡礼 三浦ふみ
◆祝福された現実、そのファンタジーへの変容 濱田欧太郎
月間テーマ ワールドユースデーに息吹く聖霊
司祭叙階当時から、世界中のカトリックの青年が集うWYDを体験し、寄り添い、見守ってきた司祭による総括です。WYDの意義がひしひしと伝わってきます。次回の韓国大会に向けて、その得難い機会を逃さないよう、決意を固めるきっかけになることでしょう。
◆ワールドユースデー体験レポート (1)島袋 凜、(2)高山 創
実際に現地に赴いた若者たちによるレポートです。興奮と感動、涙にあふれたWYDの息吹を感じてみましょう。
◆風よ! 炎よ! 私にことばを! 25 王の奴隷とならないために 小林 剛
◆京・江戸・博多、そして巴里 20 衆議院解散権は首相の伝家の宝刀か・続 南野 森
◆祈りがないと生きていけない 第9回 学校の沈黙 豊かに広がり、祈りを育む 大山江理子
◆使徒的書簡 Desiderio desideravi(切に願っていた)を読む
――教会活動の頂点であり源泉である典礼について 第9回
「典礼執行の芸術」と典礼養成 フランコ・ソットコルノラ
◆栗田隆子と、フェミニスト神学に学んでみよう! 第9回
NICEを振り返る(その1) 栗田隆子
◆イエスのたとえ――生きる希望のしるべとして 第9回 「ぶどう園の労働者」のたとえ 本多峰子
◆私とイエスとの出会い 第9回 神様との出会い(1)信仰の原点、WYDの体験 竹田治比古
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語 第9回 「レカブ」という暮らし 高橋洋成
◆つうしん
◆憲法とキリスト教 最終回 カルトとは何か――(2)自分で考え、共に読み、人生を豊かに 南野 森×森島 豊×久保文彦×小林 剛
◆シノドスとディアコニア――(2)ディアコニアとは何か? 三浦ふみ
最初の殉教者ステファノの役割であり、現代のカトリック教会では助祭と訳されている「ディアコン」と同じ語幹を持つ「ディアコニア(奉仕の務め)」は、「宣教」「典礼」と並んで教会の本質に属するものです。教会のあらゆる活動は貧しい人への奉仕なしにはあり得ないことを、シノダリティとの関連で考察していきます。
月間テーマ カルトとどう向き合うか
◆スピリチュアル・アビュースとカルト問題における信教の自由 藤田庄市
オウム真理教事件以前に、カルトの跋扈に危機感を感じ、その反社会的行為をつぶさに長年観察し、危険な本質に肉薄してきた著者からの寄稿です。被害者からの証言を通じて、旧統一教会など、過激化したカルトの非常に恐ろしい手口と巧妙なテクニックに迫ります。
◆異端なき社会のゆくえ――正統が困難な時代の信仰 岡本亮輔
パロディ宗教や、先鋭化する無神論者と創造論者の戦いなど、現代的な視点を幅広く含め、『創造論者VS.無神論者 宗教と科学の百年戦争』〈講談社刊〉の著者が、正統宗教と異端を見つめます。超教派で活況を呈するテゼ共同体や、サンティアゴ・デ・コンポステーラ巡礼など、最近の若者をとらえている動きの特徴とは何でしょうか。
◆風よ! 炎よ! 私にことばを! 26 分かち合い、傾聴、共同識別 鈴木敦詞
◆京・江戸・博多、そして巴里 21 衆議院解散権は首相の伝家の宝刀か・完 南野 森
◆祈りがないと生きていけない 第10回 少し整え日常で祈る 田邊知江
◆使徒的書簡 Desiderio desideravi(切に願っていた)を読む
――教会活動の頂点であり源泉である典礼について 第10回
典礼における司祭の格別な役割 フランコ・ソットコルノラ
◆栗田隆子と、フェミニスト神学に学んでみよう! 第10回
NICEを振り返る(その2) 栗田隆子
◆イエスのたとえ――生きる希望のしるべとして 第10回 「金持ちとラザロ」のたとえ 本多峰子
◆私とイエスとの出会い 第10回 神様との出会い(2)生きた信仰、人格的な出会い 竹田治比古
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語 第10回 「カナンの言葉」という立ち帰り 高橋洋成
◆つうしん
◆シノドスとディアコニア――(3)教会、交わりの工房 三浦ふみ
貧しい人や苦しんでいる人に仕え、聴き、学び、共に悩み苦しみ、共に喜び歩むことが教会にとっての命であり、教会が息を吹き返すかの鍵はそこにあるということを、力強い説得力をもって説明されています。教皇フランシスコの就任時からのそもそもの原点もそこにあり、教会の未来はここにかかっているのではないでしょうか。
月間テーマ いのちの尊厳を守る
監獄に入れられている人々への虐待、未だになされている死刑というものが、そもそも私たちにとって何も関係ないことでは決してないでしょう。私たちの社会全体の矛盾、苦悩が、もっとも疎外されたこの人々を取り巻く環境に凝縮的に反映されています。そもそも犯罪者が再犯しないようなケアをすることが社会を良くしていくことにつながっていく、という洞察が、現場で支援している人々によって語られています。
◆信仰を養う主日の福音 第1回 B年 待降節第1主日~主の降誕 雨宮 慧
※ご注意:雨宮師の本連載は2023年12月号から新連載(第1回)を開始します。
◆京・江戸・博多、そして巴里 22 旧統一教会への解散命令請求について 南野 森
◆風よ! 炎よ! 私にことばを! 27 世界の周縁部にある教会 有村浩一
◆祈りがないと生きていけない 最終回 共同体の祈りの力 田邊知江
◆使徒的書簡 Desiderio desideravi(切に願っていた)を読む
――教会活動の頂点であり源泉である典礼について 最終回
全世界に、福音宣教に、向かっている典礼 フランコ・ソットコルノラ
◆栗田隆子と、フェミニスト神学に学んでみよう! 最終回
誰が教会の中心なのか 栗田隆子
◆イエスのたとえ――生きる希望のしるべとして 最終回
「十人のおとめ」のたとえ、「忠実な僕と悪い僕」のたとえ、「羊と山羊」のたとえ
――終末に備えて 本多峰子
◆私とイエスとの出会い 第11回 追われたのではなく、派遣されてきた 平井栄美
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語 第10回 「アシュドドの言葉」という現実 高橋洋成
◆つうしん
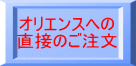
○富士山マガジンサービスからご注文

2023年 年間テーマ:かけがえのないいのちに出会う バックナンバー (著者・記事一覧)
1月号 2月号 3月号 4月号 5月号 6月号 7月号 8・9月号 10月号 11月号 12月号
○月刊『福音宣教』トップページ
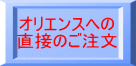
○富士山マガジンサービスからご注文
●2023年 1月号 チーム・ミニストリーの実践から 【紙版品切・電子版のみ】
新年に寄せて
時代を超えた大切な信仰の光 コンスタンチノ・コンニ・カランバ
巻頭特別企画
◆憲法とキリスト教 第1回 なぜ法学は宗教思想から距離を置くのか 南野 森×森島 豊×久保文彦
日本国憲法の中心である個人の尊厳とキリスト教は、明らかに関係があるようにみえますが、なぜそのことがあまり語られてこなかったのか。王権と教会との結び付き、宗教対立の時代背景など、近代立憲主義の成り立ちを南野先生がわかりやすく解説。
世のメタファーを読む
◆約束の地への旅、楽園への帰還 濱田欧太郎
月間テーマ チーム・ミニストリーの実践から
◆本当のチーム、共同体とは――コロナ禍の世界で見えたことを通じて 赤井悠蔵
共同体ではない教会はなく、共同宣教司牧でない司牧はない。生活支援もまた立派なチーム・ミニストリー〈共同宣教司牧〉であることなど、今の教会に一番必要な精神が語られています。
◆インタビュー 間野正孝師――旭川市内のチーム・ミニストリー 編集部
司祭が高齢化し減少していく中で、地方の教会はどのような変容を迫られているか。カトリック札幌教区旭川地区から、具体的な事例がレポートされます。
◆東京教区カテキスタ、発足から四年目 編集部
担当司祭である猪熊師や、実際のカテキスタである本誌編集担当鈴木から、東京教区のカテキスタたちがどのように活動し、いかなる問題に直面しているか、具体的に語られます。
連 載
◆京・江戸・博多、そして巴里 12 カルメル山登攀 南野 森
◆祈りがないと生きていけない 第1回 祈りとの出会い 萩原千加子
◆使徒的書簡 Desiderio desideravi(切に願っていた)を読む
――教会活動の頂点であり源泉である典礼について 第1回
書簡の動機――教会一致の視点から見た典礼 フランコ・ソットコルノラ
◆栗田隆子と、フェミニスト神学に学んでみよう! 第1回 フェミニズムとは? 栗田隆子
◆イエスのたとえ――生きる希望のしるべとして 第1回 「種を蒔く人」「成長する種」のたとえ 本多峰子
◆私とイエスとの出会い 第1回 人に最も必要なもの 今村勝己
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語 第1回 「ヘブライ語」という遺産 高橋洋成
◆つうしん
note(電子版)による記事購入↓

●2023年 2月号 カトリック学校と教区の連携
巻頭特別企画
◆憲法とキリスト教 第2回 聖書と憲法の共通点 南野 森×森島 豊×久保文彦
法実証主義に基づく実定法は、悪法でも違法ではない可能性があり、ナチズムにも利用されたため、その反省から戦後ドイツでは自然法の復権がありました。人間らしく生きるための参考書でもある聖書と日本国憲法の共通点とは。
フォーラム
◆「シノドス的教会を目指すカトリック教会」のコミュニオン――大陸ステージのための作業文書をどう読むか 原 敬子
今期シノドスの「回心と改革の旅」のために、全世界から集められた回答書では、どのようなことが考えられ、何が目指されているのか。宣教するシノドス的な教会となるための取り組みを解説。
月間テーマ カトリック学校と教区の連携
◆東北地区でのカトリック学校教員養成 土倉 相
宗教教育をすることが難しくなっていく環境の中、「カトリック学校の教職員のための養成塾」などで、長年地道に行われてきた教員同士の分かち合いや仲間作りについて知ることができます。
◆北海道カトリック学園のあゆみ 品田典子
カトリック学校の法人移管の経緯、地域の人口減少やコロナ禍、共学化への準備など、ミッションスクールにとっても厳しい時代の背景と展望について貴重な証言が語られます。
◆函館ラ・サールミッション部とカトリック函館地区青年交流会 韓 徳
札幌教区の湯川教会では、ベトナム人技能実習生への食糧支援が行われています。その活動を通して交流する函館ラ・サールミッション部。信者ではない学生たちの姿は、若者が減った現代日本の教会の希望となる成功例です。
連 載
◆風よ! 炎よ! 私にことばを! 18 聖書の当時と今 小林 剛
◆京・江戸・博多、そして巴里 13 いも九、いざ江戸へ 南野 森
◆祈りがないと生きていけない 第2回 神を知る道 佐無田 靖
◆使徒的書簡 Desiderio desideravi(切に願っていた)を読む
――教会活動の頂点であり源泉である典礼について 第2回 典礼はキリストとの出会い――書簡の意図について フランコ・ソットコルノラ
◆栗田隆子と、フェミニスト神学に学んでみよう! 第2回 耳を傾けない罪――メアリー・デイリー『教会と第二の性』を読む 栗田隆子
◆イエスのたとえ――生きる希望のしるべとして 第2回 「ぶどう園と農夫」のたとえ 本多峰子
◆私とイエスとの出会い 第2回 私の信仰体験 赤木啓子
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語 第2回 「神の言葉」という知恵 高橋洋成
◆つうしん
●2023年 3月号 小教区での自発的な活動
巻頭特別企画
◆憲法とキリスト教 第3回 人間を生かす力とは本当は何か 南野 森×森島 豊×久保文彦
人権思想は一般に近代から始まるという通念がありますが、日本国憲法の中心にもある人権思想の源は、すでに明確に「出エジプト記」や「申命記」など、聖書の中に見いだされることが語られています。
フォーラム
◆教会と学校との「懸け橋」として――教区司祭がチャプレンとして働くことの意義 鈴木 真
月間テーマ 小教区での自発的な活動
◆インタビュー 小田原教会・福祉部――地域のつなぎ役となっている教会 編集部
この教会の福祉活動は、もともとは信徒が個人や数名で地域に出ていき、粘り強く奉仕していたことが始まりです。これらの支援を教会が背後からサポートするようになり、結果的に地域のパイプ役になっていきます。教会が地域社会の中に溶け込んでいる姿に学びましょう。
◆インタビュー 大和教会・社会活動部 編集部
1980年代からボートピープルの難民を支援し、外国籍の人々を受け入れ支えてきた教会の信者たち。その支援は今も続き、このコロナ禍で真っ先に労働力から外され、明日食べるものにも事欠くような方々を大勢支えています。また、奉献生活者のサポートのもと、情報・教育格差に苦しむ子どもたちの学習支援を学生たちが行っている姿をお伝えします。
連 載
◆風よ! 炎よ! 私にことばを! 19 シノドスで迷子? 有村浩一
◆京・江戸・博多、そして巴里 14 教師のやる気、学生のやる気 南野 森
◆祈りがないと生きていけない 第3回 イエスと共に歩む道 佐無田 靖
◆使徒的書簡 Desiderio desideravi(切に願っていた)を読む
――教会活動の頂点であり源泉である典礼について 第3回
神と出会う典礼の中心に――驚き、喜び、感謝! フランコ・ソットコルノラ
◆栗田隆子と、フェミニスト神学に学んでみよう! 第3回
E・S・フィオレンツァ『彼女を記念して』を読む――ないことにされた女性の言葉を刻む 栗田隆子
◆イエスのたとえ――生きる希望のしるべとして 第3回 「善いサマリア人」のたとえ 本多峰子
◆私とイエスとの出会い 第3回 行動する中でイエスと出会い続ける 酒井育子
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語 第3回 「一つの言葉」という混乱 高橋洋成
◆この一冊 坂口ふみ著『〈個〉の誕生――キリスト教教理をつくった人びと』 編集部
◆つうしん
●2023年 4月号 教皇ベネディクト16世
巻頭特別企画
◆憲法とキリスト教 第4回 人権思想と聖書 南野 森×森島 豊×久保文彦
人権思想の裏に聖書があると言った場合、たとえば聖書の中で奴隷制が「認められている」ことをどう考えるのか。聖書の読み方にヒントが与えられます。
この人に聞く
◆「こうのとりのゆりかご」の相談室長の蓮田真琴さん 聞き手・黒川京子
「赤ちゃんポスト」が設立された経緯、海外の状況、現在の具体的な運用などについて、現責任者から直接お話を伺っています。
月間テーマ 教皇ベネディクト16世
先日逝去したベネディクト16世の若き神学者時代から、教皇となるに至るまでの変遷、他教派・他宗教とのかかわりなどについて、第一線の研究者が分かりやすく教えてくれています。
◆教皇ベネディクトゥス16世の世界史的役割 今野 元
◆教皇ベネディクト16世の帰天に寄せて 松本佐保
連 載
◆風よ! 炎よ! 私にことばを! 20 善きサマリア人の猫 鈴木敦詞
◆京・江戸・博多、そして巴里 15 憲法とはどのようなものか 南野 森
◆祈りがないと生きていけない 第4回 識別のいのり 原 敬子
◆使徒的書簡 Desiderio desideravi(切に願っていた)を読む
――教会活動の頂点であり源泉である典礼について 第4回
典礼は過越の神秘の宴、体験 フランコ・ソットコルノラ
◆栗田隆子と、フェミニスト神学に学んでみよう! 第4回 ローズマリー・R・リューサー
『性差別と神の語りかけ』を読む――女性が「自己を空しく」するとは何か? 栗田隆子
◆エッセイ 言葉や口先だけではなく、行いをもって…… 栗田隆子
◆イエスのたとえ――生きる希望のしるべとして 第4回 「仲間を赦さない家来」のたとえ 本多峰子
◆私とイエスとの出会い 第4回 昔も、今も、これからも共に歩んでくれる神様と 川島瑠里子
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語 第4回 「ベニヤミン」という希望 高橋洋成
◆つうしん
●2023年 5月号 病者に寄り添う人々
巻頭特別企画
◆憲法とキリスト教 第5回 憲法における内面の自由とは何か 南野 森×森島 豊×久保文彦×小林 剛
日本国憲法の中で最も重要な第13条で、尊重されなければならないとされている「個人」とは、一体何か。憲法学者南野先生が分かりやすく教えてくれます。
フォーラム
◆『証し――日本のキリスト者』著者 最相葉月さんインタビュー 編集部
キリスト者150名以上に密着取材し、6年がかりで完成された日本全国のキリスト者の「証し」を集めたこれまで類例のないノンフィクション作家へのインタビューです。諸宗派の異なった感じ方を内側、また外側から垣間見ることができます。
月間テーマ 病者に寄り添う人々
◆インタビュー 大野高志さん 編集部
緩和ケア病棟で、これまで出会い、また別れていった大勢の人々の声の力に支えられて働く大野牧師の姿に学ぶことができます。
◆インタビュー 漆原めぐみさん 編集部
社会から疎外された人々に寄り添う日々から、看取る日々へ、医療ソーシャルワーカーとしての召命にいたるまでにどのような導きがあったのか、分かち合ってくださいました。
◆病者の傍らで 中尾実紀子
長崎県五島で医師として多くの人の生き死ににかかわるシスター中尾の姿に、路上の人にイエスを見たマザー・テレサの姿が重なります。
連 載
◆風よ! 炎よ! 私にことばを! 21 筒井哲郎さんの思い出 久保文彦
◆京・江戸・博多、そして巴里 16 憲法とはどのようなものか・続 南野 森
◆祈りがないと生きていけない 第5回 愛と知恵の体験 片柳弘史
◆使徒的書簡 Desiderio desideravi(切に願っていた)を読む
――教会活動の頂点であり源泉である典礼について 第5回
典礼において、人間の聖化が感覚的なしるしによって示され、実現される フランコ・ソットコルノラ
◆栗田隆子と、フェミニスト神学に学んでみよう! 第5回 堀江有里
『「レズビアン」という生き方』を読む――誰が何と言おうとわたしはいま、ここにいる 栗田隆子
◆イエスのたとえ――生きる希望のしるべとして 第5回
「放蕩息子」のたとえ、「見失った羊」のたとえ、「無くした銀貨」のたとえ 本多峰子
◆私とイエスとの出会い 第5回 私と神さまとのつながり 髙木聖美
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語 第5回 「シボレト」という連帯 高橋洋成 高橋洋成
◆つうしん
●2023年 6月号 移動・移住する人々とともに
巻頭特別企画
◆憲法とキリスト教 第6回 天皇型人権 南野 森×森島 豊×久保文彦×小林 剛
戦前から日本で使われ定着していた「人権」という言葉の意味が、いかに戦後の日本国憲法が語る人権と異なっていたか、衝撃を受けます。それは今も現代日本の人権に関する偏った考え方の水面下に依然、存在し、影響し続けているのかもしれません。
世のメタファーを読む
◆開かれた部屋と閉ざされた部屋 濱田欧太郎
月間テーマ 移動・移住する人々とともに
◆インタビュー 命の心配をせずに暮らしたいだけ――ミャンマーから家族の声 安田菜津紀
運命に翻弄されミャンマーから日本へ逃亡せざるを得ず、いまも苦しみの中でたくましく生きる家族の苦闘の歴史が浮き彫りになっています。現代日本に移動・移住する人々にとって、自由と人権の理不尽かつ暴力的な制限がどのくらい重く課せられているのか、実感できる内容です。
◆インタビュー ベトナムからの人々を支援する 編集部
――ペトロマリア・グェン・フ―・ヒェン神父
――シスター・マリア・レ・ティ・ラン
――ヨセフ・グエン・タン・ニャー神父
ボートピープルを40年以上支援し続けるベトナム人司祭。また、元ボートピープルであり、今はベトナム人のあらゆる相談を受ける専門職であるシスター。そして、日本の小教区の助任司祭であり、わたしたちの教会のために働きながら、空いている時間をベトナム人司牧に捧げている司祭。それぞれが相互に支え合いながら共に支援活動をしている実際の様子を知ることができます。
連 載
◆風よ! 炎よ! 私にことばを! 22 どうする地方の教会 伊能哲大
◆京・江戸・博多、そして巴里 17 憲法とはどのようなものか・完 南野 森
◆祈りがないと生きていけない 第6回 サダナ黙想の指導をしながら(1) 植栗 彌
◆使徒的書簡 Desiderio desideravi(切に願っていた)を読む
――教会活動の頂点であり源泉である典礼について 第6回
活きた典礼のための養成――典礼の養成はシンボル(象徴)を理解することから始まる フランコ・ソットコルノラ
◆栗田隆子と、フェミニスト神学に学んでみよう! 第6回 グスタボ・グティエレス
『解放の神学』を読む――フェミニスト神学のベースに流れるもの 栗田隆子
◆イエスのたとえ――生きる希望のしるべとして 第6回
「タラントン」のたとえと「ムナ」のたとえ 本多峰子
◆私とイエスとの出会い 第6回 福音書のつづき 橘 依理子
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語 第6回 「アシュタロト」という緩み 高橋洋成
◆つうしん
●2023年 7月号 いのちを脅かす原発を廃絶するために
巻頭特別企画
◆憲法とキリスト教 第7回 信仰者の心に培われた“権理”意識 南野 森×森島 豊×久保文彦×小林 剛
日本の歴史を振り返り、人権意識や抵抗権はキリスト者の信仰によって培われたという否定しがたい面が指摘されています。この人権意識、抵抗権が、日本でどのように為政者によって危険視され弾圧され、日本国家建設のために歪んだものとなり、その歪みが今に至る矛盾の背景となっていったのかが語られます。
フォーラム
◆これまでのシノドスの歩みとアジアシノドス体験記――「聞く」ことの大切さ 西村桃子
月間テーマ いのちを脅かす原発を廃絶するために
◆政府の原発回帰政策の問題点 松久保 肇
政府の原発回帰政策の根本的な矛盾と問題点を、日本で最も詳しい専門家の一人が総合的に分析。原発は非常に高額なコストのかかる不合理かつ危険で安定性のない技術。日本の原発メーカーも、技術維持のための海外での建設誘致にことごとく失敗。メーカー側の資金ではその高額な費用が捻出できず、税金である国家予算を投与しようとしています。電気代の高騰にも直接つながる非常に問題視すべき事態です。
◆原発政策大転換の愚か 内藤新吾
今回の政策転換の政府の隠れた意図を内藤師が指摘する内容になっています。政府は脱炭素への世界の世論を隠れ蓑に、安全な耐用年数を超えた原発の危険な延長使用を目立たないよう巧妙に進め、核兵器使製造を目的とするとしか見えない燃料サイクルの計画を告発する内容となっています。今こそキリスト者は声あげるべき時です。
※お詫びと訂正 31頁の訂正箇所
◆自分からはじめるエネルギー転換 木村護郎クリストフ
ドイツの原発政策を追ってきた木村氏から、ご自身の家庭で実践している、個人の自宅の脱炭素化の例を紹介していただきました。勇気と知恵の与えられる報告です。
連 載
◆風よ! 炎よ! 私にことばを! 23 読者交流会へのお誘い 小林 剛
◆京・江戸・博多、そして巴里 18 憲法に緊急事態条項は必要か 南野 森
◆祈りがないと生きていけない 第7回 サダナ黙想の指導をしながら(2) 植栗 彌
◆使徒的書簡 Desiderio desideravi(切に願っていた)を読む
――教会活動の頂点であり源泉である典礼について 第7回
典礼におけるしるし――シンボルと典礼「文化内化」 フランコ・ソットコルノラ
◆栗田隆子と、フェミニスト神学に学んでみよう! 第7回 マルセラ・アルトハウス=リード
『下品な神学 Indecent Theology』を読む――聖書をクィア(ヘンダイ)として解釈すること 栗田隆子
◆イエスのたとえ――生きる希望のしるべとして 第7回 「不正な管理人」のたとえ 本多峰子
◆私とイエスとの出会い 第7回 神様との出会い 村山雅哉
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語 第7回 「ライオン」という謎かけ 高橋洋成
◆つうしん
●2023年 8・9月号 世界各地域のシノドスの動向
巻頭特別企画
◆憲法とキリスト教 第8回 「イエス・キリスト」を語れる人は誰か 南野 森×森島 豊×久保文彦×小林 剛
フォーラム
◆新司教に聞く――(1)大分教区、森山信三師/(2)仙台教区、E・ガクタン師 編集部
月間テーマ 世界各地域のシノドスの動向
◆ドイツの教会の動向(英仏カトリック誌から) 有村浩一
ドイツ司教団が、教会の大幅な改革を目指し、性虐待問題を受けての聖職者至上主義の根絶、教会統治の全レベルでの女性参画、同性カップルの祝福などを求める決然とした姿勢を示す一方、教皇庁がブレーキをかける構図。改革を拒絶する勢力との内部分裂、霊的対話が維持できるかが焦点です。
◆フランス教区ステージと欧州大陸ステージ 三浦ふみ
教会は「もっとも小さな声」である、もっとも疎外されている人々の声、差別されている人々の声、また「地球の叫び」を聴くことが欠落していたと強調。シノダリティは、彼らの声に耳を傾けるという実践なしには、変容はないと指摘しています。
◆インタビュー キハーノ司教(ペルー)に聞く 聞き手・山野内倫昭司教
ラテンアメリカとカリブ海諸国では、教会における女性の主体性が欠如する構造に目を向け、性虐待への取り組みの強化、先住民族やアマゾンの自然と移住移動者と難民への配慮について意識を高める必要性も課題に。シノドスの障害に聖職者至上主義を挙げています。
◆インタビュー 李尙潤師(韓国)に聞く 編集部
韓国の教会ではシノドスのために、SNSを活用し、用意周到な聞き取りを行って徹底的な調査を実施。聖職者の権威主義による傾聴の欠落、勇気ある発言のなさ、青少年の意見を聞かず疎外し、司祭だけでなく全員の共同責任という認識不足、社会との対話の不足を挙げ、識別のための養成の必要性を宣言しました。
連 載
◆風よ! 炎よ! 私にことばを! 24 大人こそ『こじか』 萩原千加子
◆京・江戸・博多、そして巴里 19 衆議院解散権は首相の伝家の宝刀か 南野 森
◆祈りがないと生きていけない 第第8回 真命山での生活 三谷博子
◆使徒的書簡 Desiderio desideravi(切に願っていた)を読む
――教会活動の頂点であり源泉である典礼について 第8回
典礼を生きるために必要な養成と方法 フランコ・ソットコルノラ
◆栗田隆子と、フェミニスト神学に学んでみよう! 第8回
『日本におけるキリスト教フェミニスト運動史』を読む 栗田隆子
◆イエスのたとえ――生きる希望のしるべとして 第8回 ファリサイ派の人と徴税人」のたとえ 本多峰子
◆私とイエスとの出会い 第8回 さりげない言葉、関わりから 梅木明代
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語 第8回 「アラム語」という文明 高橋洋成
◆つうしん
●2023年 10月号 ワールドユースデーに息吹く聖霊
巻頭特別企画
◆憲法とキリスト教 第9回 カルトとは何か――(1)自分で考えさせない共同体 南野 森×森島 豊×久保文彦×小林 剛
カルト化は宗教だけではなく、あらゆる団体において起きうるという重要な指摘がなされています。社会一般にカルト的なものが蔓延していないか、今一度考え直すために役立つ、貴重な話し合いになっています。
フォーラム
◆シノドスとディアコニア――(1)聖ラウレンチオネットワークのルルド巡礼 三浦ふみ
世のメタファーを読む
◆祝福された現実、そのファンタジーへの変容 濱田欧太郎
月間テーマ ワールドユースデーに息吹く聖霊
◆ワールドユースデーが生み出すもの 松村繁彦
司祭叙階当時から、世界中のカトリックの青年が集うWYDを体験し、寄り添い、見守ってきた司祭による総括です。WYDの意義がひしひしと伝わってきます。次回の韓国大会に向けて、その得難い機会を逃さないよう、決意を固めるきっかけになることでしょう。
◆ワールドユースデー体験レポート (1)島袋 凜、(2)高山 創
実際に現地に赴いた若者たちによるレポートです。興奮と感動、涙にあふれたWYDの息吹を感じてみましょう。
連 載
◆風よ! 炎よ! 私にことばを! 25 王の奴隷とならないために 小林 剛
◆京・江戸・博多、そして巴里 20 衆議院解散権は首相の伝家の宝刀か・続 南野 森
◆祈りがないと生きていけない 第9回 学校の沈黙 豊かに広がり、祈りを育む 大山江理子
◆使徒的書簡 Desiderio desideravi(切に願っていた)を読む
――教会活動の頂点であり源泉である典礼について 第9回
「典礼執行の芸術」と典礼養成 フランコ・ソットコルノラ
◆栗田隆子と、フェミニスト神学に学んでみよう! 第9回
NICEを振り返る(その1) 栗田隆子
◆イエスのたとえ――生きる希望のしるべとして 第9回 「ぶどう園の労働者」のたとえ 本多峰子
◆私とイエスとの出会い 第9回 神様との出会い(1)信仰の原点、WYDの体験 竹田治比古
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語 第9回 「レカブ」という暮らし 高橋洋成
◆つうしん
●2023年 11月号 カルトとどう向き合うか
巻頭特別企画
◆憲法とキリスト教 最終回 カルトとは何か――(2)自分で考え、共に読み、人生を豊かに 南野 森×森島 豊×久保文彦×小林 剛
フォーラム
◆シノドスとディアコニア――(2)ディアコニアとは何か? 三浦ふみ
最初の殉教者ステファノの役割であり、現代のカトリック教会では助祭と訳されている「ディアコン」と同じ語幹を持つ「ディアコニア(奉仕の務め)」は、「宣教」「典礼」と並んで教会の本質に属するものです。教会のあらゆる活動は貧しい人への奉仕なしにはあり得ないことを、シノダリティとの関連で考察していきます。
月間テーマ カルトとどう向き合うか
◆「カルト」教団の特徴とその抑制 島薗 進
◆スピリチュアル・アビュースとカルト問題における信教の自由 藤田庄市
オウム真理教事件以前に、カルトの跋扈に危機感を感じ、その反社会的行為をつぶさに長年観察し、危険な本質に肉薄してきた著者からの寄稿です。被害者からの証言を通じて、旧統一教会など、過激化したカルトの非常に恐ろしい手口と巧妙なテクニックに迫ります。
◆異端なき社会のゆくえ――正統が困難な時代の信仰 岡本亮輔
パロディ宗教や、先鋭化する無神論者と創造論者の戦いなど、現代的な視点を幅広く含め、『創造論者VS.無神論者 宗教と科学の百年戦争』〈講談社刊〉の著者が、正統宗教と異端を見つめます。超教派で活況を呈するテゼ共同体や、サンティアゴ・デ・コンポステーラ巡礼など、最近の若者をとらえている動きの特徴とは何でしょうか。
連 載
◆風よ! 炎よ! 私にことばを! 26 分かち合い、傾聴、共同識別 鈴木敦詞
◆京・江戸・博多、そして巴里 21 衆議院解散権は首相の伝家の宝刀か・完 南野 森
◆祈りがないと生きていけない 第10回 少し整え日常で祈る 田邊知江
◆使徒的書簡 Desiderio desideravi(切に願っていた)を読む
――教会活動の頂点であり源泉である典礼について 第10回
典礼における司祭の格別な役割 フランコ・ソットコルノラ
◆栗田隆子と、フェミニスト神学に学んでみよう! 第10回
NICEを振り返る(その2) 栗田隆子
◆イエスのたとえ――生きる希望のしるべとして 第10回 「金持ちとラザロ」のたとえ 本多峰子
◆私とイエスとの出会い 第10回 神様との出会い(2)生きた信仰、人格的な出会い 竹田治比古
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語 第10回 「カナンの言葉」という立ち帰り 高橋洋成
◆つうしん
●2023年 12月号 いのちの尊厳を守る
フォーラム
◆シノドスとディアコニア――(3)教会、交わりの工房 三浦ふみ
貧しい人や苦しんでいる人に仕え、聴き、学び、共に悩み苦しみ、共に喜び歩むことが教会にとっての命であり、教会が息を吹き返すかの鍵はそこにあるということを、力強い説得力をもって説明されています。教皇フランシスコの就任時からのそもそもの原点もそこにあり、教会の未来はここにかかっているのではないでしょうか。
月間テーマ いのちの尊厳を守る
◆座談会 死刑問題と社会の病理 雨宮処凛×クマ×塩田祐子×柳川朋毅
監獄に入れられている人々への虐待、未だになされている死刑というものが、そもそも私たちにとって何も関係ないことでは決してないでしょう。私たちの社会全体の矛盾、苦悩が、もっとも疎外されたこの人々を取り巻く環境に凝縮的に反映されています。そもそも犯罪者が再犯しないようなケアをすることが社会を良くしていくことにつながっていく、という洞察が、現場で支援している人々によって語られています。
連 載
◆信仰を養う主日の福音 第1回 B年 待降節第1主日~主の降誕 雨宮 慧
※ご注意:雨宮師の本連載は2023年12月号から新連載(第1回)を開始します。
◆京・江戸・博多、そして巴里 22 旧統一教会への解散命令請求について 南野 森
◆風よ! 炎よ! 私にことばを! 27 世界の周縁部にある教会 有村浩一
◆祈りがないと生きていけない 最終回 共同体の祈りの力 田邊知江
◆使徒的書簡 Desiderio desideravi(切に願っていた)を読む
――教会活動の頂点であり源泉である典礼について 最終回
全世界に、福音宣教に、向かっている典礼 フランコ・ソットコルノラ
◆栗田隆子と、フェミニスト神学に学んでみよう! 最終回
誰が教会の中心なのか 栗田隆子
◆イエスのたとえ――生きる希望のしるべとして 最終回
「十人のおとめ」のたとえ、「忠実な僕と悪い僕」のたとえ、「羊と山羊」のたとえ
――終末に備えて 本多峰子
◆私とイエスとの出会い 第11回 追われたのではなく、派遣されてきた 平井栄美
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語 第10回 「アシュドドの言葉」という現実 高橋洋成
◆つうしん
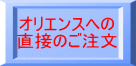
○富士山マガジンサービスからご注文