月刊 福音宣教
2026年 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
2025年 年間テーマ:失くした羊を探し求めて バックナンバー (著者・記事一覧)
1月号 2月号 3月号 4月号 5月号 6月号 7月号 8・9月号 10月号 11月号 12月号
○月刊『福音宣教』トップページ
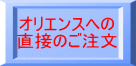
○富士山マガジンサービスからご注文
※ご注意:(富士山マガジンサービスサイトでは) 自動継続設定は新規注文時に「ご注文内容の確認」画面の「配送先変更/自動継続設定」ボタンより選択可能で、選択をされていない場合は、はじめから「自動継続する」にチェックマークが入った状態となっております。自動継続を希望されない場合は、ご注文時に「自動継続する」のチェックマークを外してご注文ください。
※電子版 note 月刊『福音宣教』は最新刊発行の1ヶ月後(毎月15日前後/8月休刊)に配信いたします。
ともに旅し、福音の喜びを証しする教会をめざして コンスタンチノ・コンニ・カランバ(オリエンス宗教研究所所長)
◆日本カトリック司教団『見よ、それはきわめてよかった――総合的な(インテグラル)エコロジーへの招き』を読む 1 文書の背景・特徴・全体構成、および第一部「観る」その① 成井大介(「ラウダ―ト・シ」デスク責任司教)×瀬本正之(「ラウダ―ト・シ」デスク)×光延一郎(イエズス会司祭、上智大学神学部教授)
聖職者の性的虐待で揺れる中、フランスの成人洗礼の数の増加というニュースが世間を驚かせています。それに対して教会関係者が喜ぶことは不謹慎であるとの意見もあります。総合的なエコロジーに取り組むために、私たちを取り巻く現実とマスコミ、メディア、SNSの役割について、改めて考え直してみるべき時期にあるのではないでしょうか。
◆旅する「わたし」の、見たり、聴いたり、考えたり――フランス編 ①「第一の手紙、見たこと」 原 敬子(援助修道会会員、上智大学神学部教授)
◆シノドス第二会期概要――宣教するシノドス教会になるためには 西村桃子(セルヴィー・エヴァンジェリー宣教者の会宣教師)
シノドス第二会期が終わりました。しかし、シノドスはこれから始まる、というのが、シノドスに参加した三者に共通するメッセージです。バチカンはすでに驚くべき変貌を遂げ、教区の仕組みも変わっていくようです。そこで「霊における会話」の効果的な実践が鍵ですが、成功に導くにはあきらめずに辛抱強く続けるべきだということが指摘されています。
◆インタビュー ともに歩む宣教、その先にある場所――シノドスの始まり、これからの道のり 菊地 功(枢機卿、日本カトリック司教協議会会長、東京教区大司教、国際カリタス総裁)
◆インタビュー シノドスの目的と、その経緯、意義 弘田しずえ(べリス・メルセス宣教修道女会会員、タリタ・クム日本運営委員長、カトリック正義と平和協議会専門委員)
◆見失われた羊に寄りそって 1 見失われた羊 英 隆一朗(イエズス会司祭)
◆京・江戸・博多、そして巴里 34 SNSは民主政治を乗っ取るか 南野 森(憲法学者)
◆旧約聖書のダメ男たち――ドキッ! それ私のこと? 1 モーセ 北 博(聖書学者)
◆ペラギウス派と古代東方神学――具体的自由としての恩恵 1
プロローグ(1)――自由意志と恩恵の協働 山田 望(南山大学教授)
エキュメニカルな観点から、従来ほとんど顧みられてこなかったペラギウス派と東方教会の伝統とのつながりの、思わぬ側面を照らしていきます。そこから見えてくる義認(義化)の理解と、東方教会の隠修士的な伝統を、恩寵との協働という側面から調和的に考察していきます。
◆信仰を養う主日の福音 13 C年 神の母聖マリア~年間第3主日 雨宮 慧(東京教区司祭)
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語(続編) 第1回 「新年」という暮らし 高橋洋成(セム語〈ヘブライ語〉学者)
◆つうしん
noteによる記事購入↓

○月刊『福音宣教』トップページへ
◆日本カトリック司教団『見よ、それはきわめてよかった――総合的な(インテグラル)エコロジーへの招き』を読む 2 第一部「観る」その② 成井大介(「ラウダ―ト・シ」デスク責任司教)×瀬本正之(「ラウダ―ト・シ」デスク)×光延一郎(イエズス会司祭、上智大学神学部教授)
◆インタビュー シノドスを取り巻くうねり(1)――女性助祭をめぐる流れ 弘田しずえ(べリス・メルセス宣教修道女会会員、タリタ・クム日本運営委員長、カトリック正義と平和協議会専門委員)
女性助祭について、最終文書にまとめられる前の、バチカンでのシノドスの流れを克明に描写。もっとも注目された問題の一つであり、1000以上の提案が出されたにもかかわらず、最終報告書のたたき台がどのようになったかについて触れられています。
◆旅する「わたし」の、見たり、聴いたり、考えたり――フランス編 ②「聴いたこと」 原 敬子(援助修道会会員、上智大学神学部教授)
◆尊者北原怜子の愛と信仰――試練を通して脱自の深みに 澤田愛子(生命倫理・ホロコースト研究者)
『言問橋の星の下で――北原怜子と蟻の街』(聖母の騎士社)の著者です。「尊者」(福者の一つ手前)の称号を持つ北原怜子の生涯を、ただ讃えるだけではなく、その人間的な側面、苦難、誹謗中傷、拒否を含めて伝える内容。命を懸けて虐げられている人に寄り添い、育っていった聖性に圧倒されます。
◆無実の死刑囚・袴田巖さんを救う会 構成 門間幸枝(「無実の死刑囚・袴田巖さんを救う会」副代表)
2024年9月26日、ついに無罪判決。粘り強く座り込みを続けた、「無実の死刑囚・袴田巖さんを救う会」が裁判所に提出した請願書の一部を公開。極限的状況で国家に人生を奪われた袴田さんに寄り添い、人生の大半を使って権力の横暴に真っ向から反対し続けてきた人々の叫び、訴えから学びます。
◆インタビュー 非正規雇用者の砦を築く(上) 清水直子(プレカリアートユニオン執行委員長)
非正規雇用者でも誰でも入れる互助組織としての労働組合「プレカリアートユニオン」の執行委員長へのインタビュー。立ち上げに至る背景と、その初期の困難、また類似の労働組合や『週刊金曜日』などとの関係。不正に対して闘う人々の人脈の中から形成された本格労組の奮闘がわかる貴重な内容です。
◆風よ! 炎よ! 私にことばを! 36 み言葉から想像を広げる 小林 剛(本誌編集長)
◆見失われた羊に寄りそって 2 優生思想の中で生きる私たち 英 隆一朗(イエズス会司祭)
◆京・江戸・博多、そして巴里 35 第15回南野ゼミ東京研修旅行 南野 森(憲法学者)
◆旧約聖書のダメ男たち――ドキッ! それ私のこと? 2 アブラハム 北 博(聖書学者)
◆ペラギウス派と古代東方神学――具体的自由としての恩恵 2
プロローグ(2)――挫折、出会い、そして復活 山田 望(南山大学教授)
◆信仰を養う主日の福音 14 C年 主の奉献~年間第7主日 雨宮 慧(東京教区司祭)
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語(続編) 第2回 「アラモト」という旋律 高橋洋成(セム語〈ヘブライ語〉学者)
◆つうしん
noteによる記事購入↓

○月刊『福音宣教』トップページへ
◆日本カトリック司教団『見よ、それはきわめてよかった――総合的な(インテグラル)エコロジーへの招き』を読む 3 第二部「識別するDISCERN」その①「1 時のしるしを照らすみことばの光」
ヨゼフ・アベイヤ(福岡教区司教、「ラウダ―ト・シ」デスク担当司教)×荒川千衣子(「ラウダ―ト・シ」デスクメンバー)×光延一郎(イエズス会司祭、上智大学神学部教授)
◆インタビュー シノドスを取り巻くうねり(2)――LGBTQA+問題を見つめ、見えてくること 弘田しずえ(べリス・メルセス宣教修道女会会員、タリタ・クム日本運営委員長、カトリック正義と平和協議会専門委員)
2023年12月18日、教理庁から「変則的カップルの祝福」という文書が出されましたが、これにアフリカのグループから大反対の声が出るなど、大きく揺れている様子が伝わってきます、教皇は率先してシノドス会期中に当事者たちと会い、友好的な話し合いがもたれていました。第一会期と比較して、第二会期のシノドス全体では彼らに対する排除や拒絶は減ってきて、よりフレンドリーで人間的な話し合いが持たれていたということです。
◆旅する「わたし」の、見たり、聴いたり、考えたり――フランス編 ③「第三の手紙、考えたこと」 原 敬子(援助修道会会員、上智大学神学部教授)
◆ユダヤ教、キリスト教とパレスチナ――キリスト教シオニズムの歴史を考える 早尾貴紀(東京経済大学教授)
シオニズムの起源はユダヤ教ではなく、キリスト教にあります。十字軍を発端に宗教を理由に領土を侵略することが始まり、下って一九世紀ではさらにプロテスタントの一部にユダヤ人の王国を復活させることが救済の一段階となるという思想が流行、それに影響を受けたユダヤ人がシオニズム運動を起こし、現代に至っています。
◆インタビュー 「ゆりかご」の記憶から 宮津航一(ふるさと元気子ども食堂代表、一般社団法人子ども大学くまもと理事長)
「こうのとりのゆりかご」に預けられ、里親に育てられた著者は現在、大学生です。講演活動などをする他、地域全体で身寄りのない子どもたちを育てていこうという願いの中で、「子ども大学」や子ども食堂、またファミリーホームでの仕事を行うなど、当事者ならではの福祉活動を模索する姿に感銘を受けます。
◆インタビュー 非正規雇用者の砦を築く(下) 清水直子(プレカリアートユニオン執行委員長)
非正規雇用者でも誰でも入れる互助組織としての労働組合「プレカリアートユニオン」の執行委員長へのインタビュー2回目。話し合いによる解決ができたケースが9割以上という高い率を誇る秘訣について、労働問題だけでなく、もめごとを和解への導く数多くのヒントを掲載。
◆見失われた羊に寄りそって 3 「心失者」に生きる価値はあるか 英 隆一朗(イエズス会司祭)
◆京・江戸・博多、そして巴里 36 皇位継承と男女平等 南野 森(憲法学者)
◆旧約聖書のダメ男たち――ドキッ! それ私のこと? 3 ヤコブ 北 博(聖書学者)
◆ペラギウス派と古代東方神学――具体的自由としての恩恵 3
ペラギウス像と課題(1)――排斥の外的要因 山田 望(南山大学教授)
◆信仰を養う主日の福音 15 C年 年間第8主日~四旬節第4主日 雨宮 慧(東京教区司祭)
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語(続編) 第3回 「第八調」という演奏 高橋洋成(セム語〈ヘブライ語〉学者)
◆つうしん
noteによる記事購入↓

○月刊『福音宣教』トップページへ
◆日本カトリック司教団『見よ、それはきわめてよかった――総合的な(インテグラル)エコロジーへの招き』を読む 4 第二部「識別するDISCERN」その②「2 時のしるしに目を凝らす教皇の奉仕職」
ヨゼフ・アベイヤ(福岡教区司教、「ラウダ―ト・シ」デスク担当司教)×荒川千衣子(「ラウダ―ト・シ」デスクメンバー)×光延一郎(イエズス会司祭、上智大学神学部教授)
◆座談会 長野県北信地区、信徒の同伴者チーム 編集部
元気で活気のある長野教会では、横浜教区の掲げる共同宣教司牧方針のもと、早くから教会に初めて来られた方々のための同伴者が養成されていました。現在、大勢の同伴者たちが育ち、入門講座や結婚講座も信徒が担当し、受洗者は30名を超えているそうです。
◆殉教者の記憶と歴史化をめぐって 小俣ラポー日登美(京都大学白眉センター特定教授)
カトリックがプロテスタントに激しく対抗していた時代、列聖、列福は迷信だとの批判を避けるために膨大で厳密な書類審査を行うように。列聖された長崎二十六聖人はすばらしい信仰の先輩ですが、多くの名もない市井の信仰者たちは歴史の記録にも残らないことに気づかされます。
◆中世のキリシタンと辞書 中野 遙(上智大学基盤教育センター特任助教)
江戸時代に入る前から、宣教師たちがどのように宣教のために必須の書物、特に辞書を編纂し、発展させてきたかを研究する著者。迫害期に活動ができなくなった宣教者たちは、この時期に現代から見ても画期的で、完成された辞書を作り上げていた様子が伝わってきます。
◆インタビュー 『きみの色』監督に聞く 山田尚子(アニメ演出家・監督、アニメーター)
アニメ映画「きみの色」は、長崎・五島の教会やミッションスクールを訪れ、人々に話を聞き、じっくりと構想が練られた作られた作品であることが伝わってきます。この時代に「信じることができる人を描きたい」と語る監督の話に耳を澄ましてみましょう。
◆見失われた羊に寄りそって 4 合理的配慮から福音的配慮へ 英 隆一朗(イエズス会司祭)
◆京・江戸・博多、そして巴里 37 死刑について 南野 森(憲法学者)
◆風よ! 炎よ! 私にことばを! 37 シノドス後――識別しながら歩み続ける 有村浩一(本誌企画委員)
◆旧約聖書のダメ男たち――ドキッ! それ私のこと? 4 ヨナ 北 博(聖書学者)
◆ペラギウス派と古代東方神学――具体的自由としての恩恵 4
ペラギウス像と課題(1)――排斥の外的要因 山田 望(南山大学教授)
◆信仰を養う主日の福音 16 C年 四旬節第5主日~復活節第2主日 雨宮 慧(東京教区司祭)
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語(続編) 第4回 「森林」という楽園 高橋洋成(セム語〈ヘブライ語〉学者)
◆つうしん
noteによる記事購入↓

○月刊『福音宣教』トップページへ
◆日本カトリック司教団『見よ、それはきわめてよかった――総合的な(インテグラル)エコロジーへの招き』を読む 5 第二部「識別するDISCERN」その③――環境に対する識別をどう分かち合うか
ヨゼフ・アベイヤ(福岡教区司教、「ラウダ―ト・シ」デスク担当司教)×荒川千衣子(「ラウダ―ト・シ」デスクメンバー)×光延一郎(イエズス会司祭、上智大学神学部教授)
◆座談会 藤沢教会、「伝える部門」――過去を受け継ぎ、今を作り、未来へと開かれる 編集部
藤沢教会では40年前から信徒が中心になって入門講座を行っています。当初、「自分と向き合い、イエスと向き合い、共同体と向き合う」グリフィン講座で始められましたが、後に「聖書と祈り」が付け加えられました。多くの時間を分かち合いに使う、信徒中心の生き生きとした養成講座に学んでみましょう。
◆キリスト教シオニズムの歴史を考える 早尾貴紀(東京経済大学教授)
シオニズムの起源はユダヤ教ではなく、キリスト教にあると筆者は述べます。十字軍を発端に宗教を理由に領土を侵略することが始まり、下って一九世紀ではさらにプロテスタントの一部にユダヤ人の王国を復活させることが救済の一段階となるという思想が流行、それに影響を受けたユダヤ人がシオニズム運動を起こし、現代に至ると論じています。
◆モーセ五書におけるシオニズムの起源 金井美彦(日本基督教団砧教会牧師。立教大学兼任講師)
申命記7章は、約束の地で異邦人を殲滅させる思想があると確かに読み取ることができてしまう個所です。ここを文字通り、原理主義的に解釈することは大変に危険であり、現在、ガザ地区で起きているジェノサイドと無関係ではないことを示します。
◆インタビュー パレスチナにおける援助の限界と役割 金子由佳(立教大学兼任講師。国際協力NGO職員)
「気持ちを言葉にしようとするたびに、叫びたくなります。瓦礫や石と入り混じった幼い子どもたちの遺体が目に焼き付いています」。この世の地獄と言われる現在のガザ地区についてのレポート。筆者の現地友人からの肉声を交え、戦慄なしには読むことができない、文字通り言葉を失う惨状が描かれています。
◆見失われた羊に寄りそって 5 見失った1匹が群れに戻るには 英 隆一朗(イエズス会司祭)
◆京・江戸・博多、そして巴里 38 旧統一教会に対する解散命令について 南野 森(憲法学者)
◆風よ! 炎よ! 私にことばを! 38 AIの時間と人間の時間 有村浩一(本誌企画委員)
◆旧約聖書のダメ男たち――ドキッ! それ私のこと? 5 アビメレク 北 博(聖書学者)
◆ペラギウス派と古代東方神学――具体的自由としての恩恵 5
補遺―初期キリスト教の発展要因(1) 山田 望(南山大学教授)
◆信仰を養う主日の福音 17 C年 復活節第3主日~復活節第6主日 雨宮 慧(東京教区司祭)
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語(続編) 第5回 「神殿」という住まい 高橋洋成(セム語〈ヘブライ語〉学者)
◆つうしん
noteによる記事購入↓

○月刊『福音宣教』トップページへ
◆日本カトリック司教団『見よ、それはきわめてよかった――総合的な(インテグラル)エコロジーへの招き』を読む 6 第三部「行動する ACT」その①――責任ある地球市民として神の愛をあかしする
ヨゼフ・アベイヤ(福岡教区司教、「ラウダ―ト・シ」デスク担当司教)×荒川千衣子(「ラウダ―ト・シ」デスクメンバー)×光延一郎(イエズス会司祭、上智大学神学部教授)
◆岩下壮一の青春(1) 岩下壮一を創ったもの――父・山本信次郎・ケーベル 加藤和哉(聖心女子大学教授)
岩下壮一は、深い学識と幅広い教養を持ち、若者や病者のために献身した実践家であり、明治以降の日本において最も卓越したカトリック司祭の1人です。未発表資料を読み解き、彼のこれまであまり知られていなかった側面が明らかにされていく、3回連載の第1回目です。
◆社会は教会、小教区はその一部 松村繁彦(大阪高松教区司祭、札幌教区事務局長)
この50年で大きな変化を被っている札幌教区。高齢化と人的資源の減少により、筆者は11もの小教区の主任司祭を兼任。キリシタン時代にも似た状況下、長らく受け身であった信徒の役割を根本的に見直し、信徒が能動的に司祭と共同責任を担い、信徒使徒職を実行する以外に未来がないことが伝わってくる記事です。
◆長崎教区 教育現場の現状と使命 坂本久美子(純心聖母会会員、長崎純心大学学長)
長崎のミッションスクールの生徒は、信者であっても長らく教会には行っていない生徒が多いようだという現状報告がある中、先達によって培われたカトリック学校の使命、信仰教育と人格教育がますます重要であることが語られます。生涯をかけて「知恵のみちを歩み、人と世界に奉仕する」人を育てていく著者の真摯な姿勢が伝わってきます。
◆ここに教会があること――こだまする福音 大西勇史(広島教区司祭)
たとえ非常に小さな田舎の教会であっても、信徒の数は少なくとも、信仰の灯は優しく、温かいものです。傷ついた人をひきつけ、皆で助け合い、関わり合っていく姿、教会の原点の在り方を示す忘れがたい思い出を分かち合ってくださいました。
◆見失われた羊に寄りそって 6 障がいの2つのモデル 英 隆一朗(イエズス会司祭)
◆京・江戸・博多、そして巴里 39 教皇フランシスコ逝去 南野 森(憲法学者)
◆風よ! 炎よ! 私にことばを! 39 教皇フランシスコ後の懸念 伊能哲大(本誌企画委員)
◆旧約聖書のダメ男たち――ドキッ! それ私のこと? 6 サムソン 北 博(聖書学者)
◆ペラギウス派と古代東方神学――具体的自由としての恩恵 6
補遺―初期キリスト教の発展要因(2) 山田 望(南山大学教授)
◆信仰を養う主日の福音 18 C年 主の昇天~聖ペトロ 聖パウロ使徒 雨宮 慧(東京教区司祭)
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語(続編) 第6回 「風琴」という交響曲 高橋洋成(セム語〈ヘブライ語〉学者)
◆つうしん
noteによる記事購入↓

○月刊『福音宣教』トップページへ
◆日本カトリック司教団『見よ、それはきわめてよかった――総合的な(インテグラル)エコロジーへの招き』を読む 7 第三部「行動する ACT」その②――ともに歩み、ともに識別する教会共同体へ
ヨゼフ・アベイヤ(福岡教区司教、「ラウダ―ト・シ」デスク担当司教)×荒川千衣子(「ラウダ―ト・シ」デスクメンバー)×光延一郎(イエズス会司祭、上智大学神学部教授)
◆教皇フランシスコの信仰 ホアン・アイダル (Juan Carlos Haidar●イエズス会会員。上智大学神学研究科委員長)
教皇フランシスコが残してくださったものでもっとも素晴らしいものは、彼の信仰だったと、若い頃から指導を受けてきた筆者は言います。彼が他人の悪口を言っているという話は聞いたことがないそうです。謙遜さと貧しさに貫かれた態度は、一生涯を通して貫かれていました。
◆神の民である教会を活かした教皇――フランシスコ教皇を偲んで デ・ルカ・レンゾ(De Luca Renzo●イエズス会会員。日本二十六聖人記念館館長)
教皇フランシスコに謁見した人は、どんな相手であろうと「自分だけに特別に関わってくださる」と思わせることが多かったそうです。一人ひとりの人間を大切にして向き合う態度は、神の民を育て、世界を大切にし、環境を大切する心と首尾一貫してつながっていました。
◆教皇フランシスコのイザヤ書に沿ったアピール――「アフリカから手を引け!」(上) カブンディ・オノレ(Kabundi Honore●淳心会会員。オリエンス宗教研究所所長)
教皇ブランシスコは2023年、コンゴ民主共和国(以下コンゴと略)の悲惨な状況に心を痛め、38年ぶりの教皇によるコンゴ訪問を決断。豊かな資源と人材を搾取する国際社会に向かって「コンゴから手を引け! アフリカから手を引け!」と激しい訴えを行いました。「主のしもべの歌」になぞらえ、国内に居ながらにして捕囚されている民の悲惨な現状を前に、世界の人々へ問いかけが迫ります。
◆教皇フランシスコに導かれて、新たな共同体、新たな自分 山野内公司+信徒の皆様(やまのうち・ひとし●サレジオ修道会会員)
教皇フランシスコが打ち出してきた指針を誠実に、また着実に実行してきた筆者が、共に歩みをともにしてきた信徒と、フランシスコの就任から逝去までの間の歩み、その間成長してきた教会の歩みを振り返ってくださいました。
◆見失われた羊に寄りそって 7 出向いていく牧者 英 隆一朗(イエズス会司祭)
◆京・江戸・博多、そして巴里 40 決戦の夏 南野 森(憲法学者)
◆風よ! 炎よ! 私にことばを! 40 教皇フランシスコとの思い出 西村桃子(本誌企画委員)
◆旧約聖書のダメ男たち――ドキッ! それ私のこと? 7 サウル 北 博(聖書学者)
◆ペラギウス派と古代東方神学――具体的自由としての恩恵 7
教会史的問題状況 山田 望(南山大学教授)
◆信仰を養う主日の福音 19 C年 年間第14主日~年間第17主日 雨宮 慧(東京教区司祭)
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語(続編) 第7回 「りんご」という工夫 高橋洋成(セム語〈ヘブライ語〉学者)
◆つうしん
noteによる記事購入↓

○月刊『福音宣教』トップページへ
◆日本カトリック司教団『見よ、それはきわめてよかった――総合的な(インテグラル)エコロジーへの招き』を読む 最終回 第三部「行動する ACT」その③――「何倍も幸せになるためにやる」
ヨゼフ・アベイヤ(福岡教区司教、「ラウダ―ト・シ」デスク担当司教)×成井大介(新潟教区司教。「ラウダート・シ」責任司教)×伊藤幸史(新潟教区司祭。「信州風の家」代表)×荒川千衣子(さいたま教区信徒。「ラウダ―ト・シ」デスクメンバー)
◆岩下壮一の青春(2) 導かれるままに 加藤和哉(聖心女子大学教授)
◆教皇フランシスコのイザヤ書に沿ったアピール――「アフリカから手を引け!」(下) カブンディ・オノレ(淳心会会員。幣研究所所長)
◆教皇レオ14世の選出 菅原裕二 (イエズス会会員。教皇庁立グレゴリアン大学教会法学部名誉教授)
教皇レオ14世の人物像について総合的な視点で紹介されています。教会法の知識、米国出身でありながら南米での長い司牧経験、アウグスチノ会総長として、また司教、枢機卿として国際的な統治の経験、マルチリンガルであること、そしてカトリック教会初の社会教説を発表したレオ13世の後継者として、現代社会との対話を進めていくことが期待されます。
◆教皇レオ14世の誕生――聖アウグスチノの息子として 柴田弘之(聖アウグスチノ修道会会員。カトリック葛西教会主任司祭)
教皇を輩出することになったアウグスチノ会会員の立場から、その当初の驚きと、「ボブ」と呼ばれ親しまれたプレボスト総長時代の思い出や、そのころ手がけた難民や病者への実際の支援の数々のエピソードを交え、聖アウグスチノ修道会の精神、すなわち社会的・文化的違いを認め合い、一致する精神を実現する希望について綴っていただきました。
◆総長ロバート・プレボストから教皇レオ14世へ 今田昌樹(聖アウグスチノ修道会会員。聖マリア学院理事長)
プレボスト総長の時代に日本分管区長であった筆者の個人的な出会いの経験から、教皇の人となりを伺わせるエピソードの数々が紹介されています。控えめで地味に見えながらも実は本当はとても頼りになる、そういうボブ・プレボスト師の人柄についてお書きいただきました。
◆見失われた羊に寄りそって 8 2人のアメリカ人、2人の羊飼い 英 隆一朗(イエズス会司祭)
◆京・江戸・博多、そして巴里 41 ぬちぬ ちるがたん 南野 森(憲法学者)
◆風よ! 炎よ! 私にことばを! 41 パウロの言葉をたどる旅 萩原千加子(本誌企画委員)
◆旧約聖書のダメ男たち――ドキッ! それ私のこと? 8 ダビデ 北 博(聖書学者)
◆ペラギウス派と古代東方神学――具体的自由としての恩恵 8
幼児洗礼義務化への経緯――ペラギウス派排斥の教会史的前提 山田 望(南山大学教授)
◆信仰を養う主日の福音 20 C年 年間第18主日~年間第26主日 雨宮 慧(東京教区司祭)
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語(続編) 第8回 「雨」という実り 高橋洋成(セム語〈ヘブライ語〉学者)
◆つうしん
noteによる記事購入↓

○月刊『福音宣教』トップページへ
◆教会の使命とリーダーシップにおける女性の参加(1) カブンディ・オノレ(淳心会会員。幣研究所所長)
◆岩下壮一の青春(3) 20世紀のフランシスコ・ザビエル 加藤和哉(聖心女子大学教授)
◆森の護り手たちと森という護り手 濱田欧太郎(フランシスコ会士)
◆「最前線」を生きる教会 谷脇慎太郎 (横浜教区司祭、同教区事務局長)
横浜教区事務局長による教区の現状についての率直なレポートです。そこに危機があり、対処すべき問題が山積している様子を、コロナ禍の最初の兆候であった2020年のダイヤモンド・プリンセス号での集団感染に譬えています。「生き残り」ではなく、「使命を生きる」ということが問われています。
◆フードパントリー「ぶどうの木とくでん」への歩み 三上一雄(北海道出身。東京教区信徒)
最初は4人の作業チームから始まった徳田教会のフードパントリー。今では大きく成長し、地域との連携の中でつながりを作り出しています。筆者は1980年代から東京・三谷で支援活動を続けており、徳田教会を設立したフロジャック神父の精神に共鳴、今につながっています。
◆埼玉から宮崎の教会へ 若山治憲(埼玉県出身。大分教区信徒、2014年、宮崎に移住)
埼玉から宮崎の教会へ移り住んだ筆者は、夫婦で地方の小さな素朴で優しい共同体の中に溶け込み、いつしか教会の重要な役割を果たすことに。そこから宮崎の諸教会との連携や、地域の不登校の子どもたちのフリースペース設立へと広がっていった経緯を振り返っていただきました。
◆見失われた羊に寄りそって 9 羊飼いのジレンマ 英 隆一朗(イエズス会司祭)
◆京・江戸・博多、そして巴里 42 猿がどうしたという話では 南野 森(憲法学者)
◆旧約聖書のダメ男たち――ドキッ! それ私のこと? 9 イエフ 北 博(聖書学者)
◆ペラギウス派と古代東方神学――具体的自由としての恩恵 9
ペラギウス派排斥に至る教会史的経緯 山田 望(南山大学教授)
◆信仰を養う主日の福音 21 C年 年間第27主日~年間第30主日 雨宮 慧(東京教区司祭)
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語(続編) 第9回 「土」という財産 高橋洋成(セム語〈ヘブライ語〉学者)
◆つうしん
○月刊『福音宣教』トップページへ
◆第16回シノドスにおける変容(1) ジャン=クロード・オロリッシュ(ルクセンブルク大司教、枢機卿。第16回シノドス通常総会総書記)
通訳として若い頃から各シノドスに立ち会ってきた筆者(元上智大学副学長)による証言をお届けいたします。教皇フランシスコの時代、特に第16回シノドス通常総会がいかに大きな変容をし、今まさに教会が大きく開かれていく転機に差し掛かっていることを感じてみてください。
◆教会の使命とリーダーシップにおける女性の参加(2) カブンディ・オノレ(淳心会会員。幣研究所所長)
◆三位一体論形成時代における異端と現代におけるその意義 ハンス・ユーゲン・マルクス (神言修道会会員。前藤女子大学学長)
キリスト教会の中で多くの異端との闘いであったニケア公会議前後の時代、さまざまなな思潮がどのようにキリスト教の根幹となる三位一体論の形成に役割を果たしてきたか、簡潔に描かれています。
◆ニカイア信条の教理的な特色――三位一体論の形成 関川泰寛(大森めぐみ教会牧師。日本神学センター会長)
ニケア信条において、古代世界に一般的であった中期プラトン主義の神概念が聖書的な方向に明確に修正され、現代へと繋がる、創造と救済が受肉において具現化されるという神学の方向性が打ち立てられていきます。
◆もう一つの信条――使徒信条の成立と現代における意義 本城仰太(東京神学大学准教授・中渋谷教会牧師)
ニケア信条より古い使徒信条の成立の歴史を追い、広くプロテスタント、カトリックで共有されている使徒信条の現代的な意義について学べる内容となっています。
◆見失われた羊に寄りそって 10 一匹の孤独 英 隆一朗(イエズス会司祭)
◆京・江戸・博多、そして巴里 43 パリで祈る人々 南野 森(憲法学者)
◆旧約聖書のダメ男たち――ドキッ! それ私のこと? 10 ホセア 北 博(聖書学者)
◆ペラギウス派と古代東方神学――具体的自由としての恩恵 9
ペラギウス派排斥に至る教会史的経緯 山田 望(南山大学教授)
◆信仰を養う主日の福音 22 C年 死者の日~A年 待降節第1主日 雨宮 慧(東京教区司祭)
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語(続編) 第10回 「箱舟」という文化 高橋洋成(セム語〈ヘブライ語〉学者)
◆つうしん
○月刊『福音宣教』トップページへ
◆第16回シノドスにおける変容(2) ジャン=クロード・オロリッシュ(ルクセンブルク大司教、枢機卿。第16回シノドス通常総会総書記)
◆現代の「神の民」に連なって(1)――基地の街横須賀で学び考えたこと 浜崎眞実(横浜教区司祭。沖縄教区派遣)
米軍基地に隣接の神奈川県横須賀の三笠教会で基地問題に長らく取り組んでこられた筆者による総括、第1回目。この地に派遣された召命を生き、教会外組織と連携しての運動、教会内でのフィリピンコミュニティなどとの協力と粘り強い抗議、交渉によって外国籍の人々の滞在権と住居を確保するエピソードなど、行政を動かした例を学ぶことができます。
バチカンで行われた聖年の「青年の祝祭」のレポートを3本お届けいたします。
◆祈るということ、伝えていくということ 古川舞乃 (福岡教区笹岡教会信徒)
思春期におけるカトリック教会への反発と嫌悪にも関わらず、司祭との出会いによって青年会に参加し、少しずつ変容していき、バチカンへの巡礼によって得た恵みと感動の手記。人生の中で大きな宝物を得たことが伝わってきます。
◆神の恵み、心が燃えたこと 秋元 惇(札幌教区小樽教会信徒)
巡礼のクライマックスである教皇ミサの前日、夜を徹しての友との語り合い、仲間たちとの親密な交流によって信仰に燃え上がる様子を率直に、また赤裸々に綴ってくださいました。涙に溢れる巡礼の新鮮な喜びを感じてみましょう。
◆「希望の巡礼者」として 村山美遊(東京教区高輪教会信徒)
ただ感動して巡礼を終えるのではなく、「自分の教会の場で何ができるか」を具体的に考え始め、合宿やネットワークミーティングの集いなどの教区を超えた交流へと開かれ、希望の巡礼者として歩み続けている様子に心打たれます。
◆見失われた羊に寄りそって 11 羊飼いのわな――共依存 英 隆一朗(イエズス会司祭)
◆京・江戸・博多、そして巴里 44 女性首相の誕生 南野 森(憲法学者)
◆風よ! 炎よ! 私にことばを! 42 シノドス流の教会を実現するには? 有村浩一(本誌企画委員)
◆旧約聖書のダメ男たち――ドキッ! それ私のこと? 最終回 アダム 北 博(聖書学者)
◆ペラギウス派と古代東方神学――具体的自由としての恩恵 11 研究史概観 山田 望(南山大学教授)
◆主日の福音を通してみ言葉を生きる 1 A年 待降節第2主日~聖家族 山下 敦(大分教区司祭)
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語(続編) 第11回 「エベル」という理解 高橋洋成(セム語〈ヘブライ語〉学者)
◆つうしん
○月刊『福音宣教』トップページへ
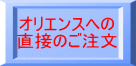
○富士山マガジンサービスからご注文

2025年 年間テーマ:失くした羊を探し求めて バックナンバー (著者・記事一覧)
1月号 2月号 3月号 4月号 5月号 6月号 7月号 8・9月号 10月号 11月号 12月号
○月刊『福音宣教』トップページ
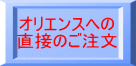
○富士山マガジンサービスからご注文
※ご注意:(富士山マガジンサービスサイトでは) 自動継続設定は新規注文時に「ご注文内容の確認」画面の「配送先変更/自動継続設定」ボタンより選択可能で、選択をされていない場合は、はじめから「自動継続する」にチェックマークが入った状態となっております。自動継続を希望されない場合は、ご注文時に「自動継続する」のチェックマークを外してご注文ください。
※電子版 note 月刊『福音宣教』は最新刊発行の1ヶ月後(毎月15日前後/8月休刊)に配信いたします。
●2025年 1月号 月間テーマ シノドス第二会期を振り返る
新年に寄せて
ともに旅し、福音の喜びを証しする教会をめざして コンスタンチノ・コンニ・カランバ(オリエンス宗教研究所所長)
特別連続座談会
◆日本カトリック司教団『見よ、それはきわめてよかった――総合的な(インテグラル)エコロジーへの招き』を読む 1 文書の背景・特徴・全体構成、および第一部「観る」その① 成井大介(「ラウダ―ト・シ」デスク責任司教)×瀬本正之(「ラウダ―ト・シ」デスク)×光延一郎(イエズス会司祭、上智大学神学部教授)
聖職者の性的虐待で揺れる中、フランスの成人洗礼の数の増加というニュースが世間を驚かせています。それに対して教会関係者が喜ぶことは不謹慎であるとの意見もあります。総合的なエコロジーに取り組むために、私たちを取り巻く現実とマスコミ、メディア、SNSの役割について、改めて考え直してみるべき時期にあるのではないでしょうか。
フォーラム
◆旅する「わたし」の、見たり、聴いたり、考えたり――フランス編 ①「第一の手紙、見たこと」 原 敬子(援助修道会会員、上智大学神学部教授)
月間テーマ シノドス第二会期を振り返る
◆シノドス第二会期概要――宣教するシノドス教会になるためには 西村桃子(セルヴィー・エヴァンジェリー宣教者の会宣教師)
シノドス第二会期が終わりました。しかし、シノドスはこれから始まる、というのが、シノドスに参加した三者に共通するメッセージです。バチカンはすでに驚くべき変貌を遂げ、教区の仕組みも変わっていくようです。そこで「霊における会話」の効果的な実践が鍵ですが、成功に導くにはあきらめずに辛抱強く続けるべきだということが指摘されています。
◆インタビュー ともに歩む宣教、その先にある場所――シノドスの始まり、これからの道のり 菊地 功(枢機卿、日本カトリック司教協議会会長、東京教区大司教、国際カリタス総裁)
◆インタビュー シノドスの目的と、その経緯、意義 弘田しずえ(べリス・メルセス宣教修道女会会員、タリタ・クム日本運営委員長、カトリック正義と平和協議会専門委員)
連 載
◆見失われた羊に寄りそって 1 見失われた羊 英 隆一朗(イエズス会司祭)
◆京・江戸・博多、そして巴里 34 SNSは民主政治を乗っ取るか 南野 森(憲法学者)
◆旧約聖書のダメ男たち――ドキッ! それ私のこと? 1 モーセ 北 博(聖書学者)
◆ペラギウス派と古代東方神学――具体的自由としての恩恵 1
プロローグ(1)――自由意志と恩恵の協働 山田 望(南山大学教授)
エキュメニカルな観点から、従来ほとんど顧みられてこなかったペラギウス派と東方教会の伝統とのつながりの、思わぬ側面を照らしていきます。そこから見えてくる義認(義化)の理解と、東方教会の隠修士的な伝統を、恩寵との協働という側面から調和的に考察していきます。
◆信仰を養う主日の福音 13 C年 神の母聖マリア~年間第3主日 雨宮 慧(東京教区司祭)
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語(続編) 第1回 「新年」という暮らし 高橋洋成(セム語〈ヘブライ語〉学者)
◆つうしん
noteによる記事購入↓

○月刊『福音宣教』トップページへ
●2025年 2月号 月間テーマ 虐げられた人とともに(1) 【紙版品切・電子版のみ】
特別連続座談会
◆日本カトリック司教団『見よ、それはきわめてよかった――総合的な(インテグラル)エコロジーへの招き』を読む 2 第一部「観る」その② 成井大介(「ラウダ―ト・シ」デスク責任司教)×瀬本正之(「ラウダ―ト・シ」デスク)×光延一郎(イエズス会司祭、上智大学神学部教授)
フォーラム
◆インタビュー シノドスを取り巻くうねり(1)――女性助祭をめぐる流れ 弘田しずえ(べリス・メルセス宣教修道女会会員、タリタ・クム日本運営委員長、カトリック正義と平和協議会専門委員)
女性助祭について、最終文書にまとめられる前の、バチカンでのシノドスの流れを克明に描写。もっとも注目された問題の一つであり、1000以上の提案が出されたにもかかわらず、最終報告書のたたき台がどのようになったかについて触れられています。
◆旅する「わたし」の、見たり、聴いたり、考えたり――フランス編 ②「聴いたこと」 原 敬子(援助修道会会員、上智大学神学部教授)
月間テーマ 虐げられた人とともに(1)
◆尊者北原怜子の愛と信仰――試練を通して脱自の深みに 澤田愛子(生命倫理・ホロコースト研究者)
『言問橋の星の下で――北原怜子と蟻の街』(聖母の騎士社)の著者です。「尊者」(福者の一つ手前)の称号を持つ北原怜子の生涯を、ただ讃えるだけではなく、その人間的な側面、苦難、誹謗中傷、拒否を含めて伝える内容。命を懸けて虐げられている人に寄り添い、育っていった聖性に圧倒されます。
◆無実の死刑囚・袴田巖さんを救う会 構成 門間幸枝(「無実の死刑囚・袴田巖さんを救う会」副代表)
2024年9月26日、ついに無罪判決。粘り強く座り込みを続けた、「無実の死刑囚・袴田巖さんを救う会」が裁判所に提出した請願書の一部を公開。極限的状況で国家に人生を奪われた袴田さんに寄り添い、人生の大半を使って権力の横暴に真っ向から反対し続けてきた人々の叫び、訴えから学びます。
◆インタビュー 非正規雇用者の砦を築く(上) 清水直子(プレカリアートユニオン執行委員長)
非正規雇用者でも誰でも入れる互助組織としての労働組合「プレカリアートユニオン」の執行委員長へのインタビュー。立ち上げに至る背景と、その初期の困難、また類似の労働組合や『週刊金曜日』などとの関係。不正に対して闘う人々の人脈の中から形成された本格労組の奮闘がわかる貴重な内容です。
連 載
◆風よ! 炎よ! 私にことばを! 36 み言葉から想像を広げる 小林 剛(本誌編集長)
◆見失われた羊に寄りそって 2 優生思想の中で生きる私たち 英 隆一朗(イエズス会司祭)
◆京・江戸・博多、そして巴里 35 第15回南野ゼミ東京研修旅行 南野 森(憲法学者)
◆旧約聖書のダメ男たち――ドキッ! それ私のこと? 2 アブラハム 北 博(聖書学者)
◆ペラギウス派と古代東方神学――具体的自由としての恩恵 2
プロローグ(2)――挫折、出会い、そして復活 山田 望(南山大学教授)
◆信仰を養う主日の福音 14 C年 主の奉献~年間第7主日 雨宮 慧(東京教区司祭)
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語(続編) 第2回 「アラモト」という旋律 高橋洋成(セム語〈ヘブライ語〉学者)
◆つうしん
noteによる記事購入↓

○月刊『福音宣教』トップページへ
●2025年 3月号 月間テーマ 虐げられた人とともに(2)
特別連続座談会
◆日本カトリック司教団『見よ、それはきわめてよかった――総合的な(インテグラル)エコロジーへの招き』を読む 3 第二部「識別するDISCERN」その①「1 時のしるしを照らすみことばの光」
ヨゼフ・アベイヤ(福岡教区司教、「ラウダ―ト・シ」デスク担当司教)×荒川千衣子(「ラウダ―ト・シ」デスクメンバー)×光延一郎(イエズス会司祭、上智大学神学部教授)
フォーラム
◆インタビュー シノドスを取り巻くうねり(2)――LGBTQA+問題を見つめ、見えてくること 弘田しずえ(べリス・メルセス宣教修道女会会員、タリタ・クム日本運営委員長、カトリック正義と平和協議会専門委員)
2023年12月18日、教理庁から「変則的カップルの祝福」という文書が出されましたが、これにアフリカのグループから大反対の声が出るなど、大きく揺れている様子が伝わってきます、教皇は率先してシノドス会期中に当事者たちと会い、友好的な話し合いがもたれていました。第一会期と比較して、第二会期のシノドス全体では彼らに対する排除や拒絶は減ってきて、よりフレンドリーで人間的な話し合いが持たれていたということです。
◆旅する「わたし」の、見たり、聴いたり、考えたり――フランス編 ③「第三の手紙、考えたこと」 原 敬子(援助修道会会員、上智大学神学部教授)
月間テーマ 虐げられた人とともに(2)
◆ユダヤ教、キリスト教とパレスチナ――キリスト教シオニズムの歴史を考える 早尾貴紀(東京経済大学教授)
シオニズムの起源はユダヤ教ではなく、キリスト教にあります。十字軍を発端に宗教を理由に領土を侵略することが始まり、下って一九世紀ではさらにプロテスタントの一部にユダヤ人の王国を復活させることが救済の一段階となるという思想が流行、それに影響を受けたユダヤ人がシオニズム運動を起こし、現代に至っています。
◆インタビュー 「ゆりかご」の記憶から 宮津航一(ふるさと元気子ども食堂代表、一般社団法人子ども大学くまもと理事長)
「こうのとりのゆりかご」に預けられ、里親に育てられた著者は現在、大学生です。講演活動などをする他、地域全体で身寄りのない子どもたちを育てていこうという願いの中で、「子ども大学」や子ども食堂、またファミリーホームでの仕事を行うなど、当事者ならではの福祉活動を模索する姿に感銘を受けます。
◆インタビュー 非正規雇用者の砦を築く(下) 清水直子(プレカリアートユニオン執行委員長)
非正規雇用者でも誰でも入れる互助組織としての労働組合「プレカリアートユニオン」の執行委員長へのインタビュー2回目。話し合いによる解決ができたケースが9割以上という高い率を誇る秘訣について、労働問題だけでなく、もめごとを和解への導く数多くのヒントを掲載。
連 載
◆見失われた羊に寄りそって 3 「心失者」に生きる価値はあるか 英 隆一朗(イエズス会司祭)
◆京・江戸・博多、そして巴里 36 皇位継承と男女平等 南野 森(憲法学者)
◆旧約聖書のダメ男たち――ドキッ! それ私のこと? 3 ヤコブ 北 博(聖書学者)
◆ペラギウス派と古代東方神学――具体的自由としての恩恵 3
ペラギウス像と課題(1)――排斥の外的要因 山田 望(南山大学教授)
◆信仰を養う主日の福音 15 C年 年間第8主日~四旬節第4主日 雨宮 慧(東京教区司祭)
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語(続編) 第3回 「第八調」という演奏 高橋洋成(セム語〈ヘブライ語〉学者)
◆つうしん
noteによる記事購入↓

○月刊『福音宣教』トップページへ
●2025年 4月号 月間テーマ 日本文化とキリスト教
特別連続座談会
◆日本カトリック司教団『見よ、それはきわめてよかった――総合的な(インテグラル)エコロジーへの招き』を読む 4 第二部「識別するDISCERN」その②「2 時のしるしに目を凝らす教皇の奉仕職」
ヨゼフ・アベイヤ(福岡教区司教、「ラウダ―ト・シ」デスク担当司教)×荒川千衣子(「ラウダ―ト・シ」デスクメンバー)×光延一郎(イエズス会司祭、上智大学神学部教授)
フォーラム
◆座談会 長野県北信地区、信徒の同伴者チーム 編集部
元気で活気のある長野教会では、横浜教区の掲げる共同宣教司牧方針のもと、早くから教会に初めて来られた方々のための同伴者が養成されていました。現在、大勢の同伴者たちが育ち、入門講座や結婚講座も信徒が担当し、受洗者は30名を超えているそうです。
月間テーマ 日本文化とキリスト教
◆殉教者の記憶と歴史化をめぐって 小俣ラポー日登美(京都大学白眉センター特定教授)
カトリックがプロテスタントに激しく対抗していた時代、列聖、列福は迷信だとの批判を避けるために膨大で厳密な書類審査を行うように。列聖された長崎二十六聖人はすばらしい信仰の先輩ですが、多くの名もない市井の信仰者たちは歴史の記録にも残らないことに気づかされます。
◆中世のキリシタンと辞書 中野 遙(上智大学基盤教育センター特任助教)
江戸時代に入る前から、宣教師たちがどのように宣教のために必須の書物、特に辞書を編纂し、発展させてきたかを研究する著者。迫害期に活動ができなくなった宣教者たちは、この時期に現代から見ても画期的で、完成された辞書を作り上げていた様子が伝わってきます。
◆インタビュー 『きみの色』監督に聞く 山田尚子(アニメ演出家・監督、アニメーター)
アニメ映画「きみの色」は、長崎・五島の教会やミッションスクールを訪れ、人々に話を聞き、じっくりと構想が練られた作られた作品であることが伝わってきます。この時代に「信じることができる人を描きたい」と語る監督の話に耳を澄ましてみましょう。
連 載
◆見失われた羊に寄りそって 4 合理的配慮から福音的配慮へ 英 隆一朗(イエズス会司祭)
◆京・江戸・博多、そして巴里 37 死刑について 南野 森(憲法学者)
◆風よ! 炎よ! 私にことばを! 37 シノドス後――識別しながら歩み続ける 有村浩一(本誌企画委員)
◆旧約聖書のダメ男たち――ドキッ! それ私のこと? 4 ヨナ 北 博(聖書学者)
◆ペラギウス派と古代東方神学――具体的自由としての恩恵 4
ペラギウス像と課題(1)――排斥の外的要因 山田 望(南山大学教授)
◆信仰を養う主日の福音 16 C年 四旬節第5主日~復活節第2主日 雨宮 慧(東京教区司祭)
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語(続編) 第4回 「森林」という楽園 高橋洋成(セム語〈ヘブライ語〉学者)
◆つうしん
noteによる記事購入↓

○月刊『福音宣教』トップページへ
●2025年 5月号 月間テーマ ユダヤ教、キリスト教とパレスチナ
特別連続座談会
◆日本カトリック司教団『見よ、それはきわめてよかった――総合的な(インテグラル)エコロジーへの招き』を読む 5 第二部「識別するDISCERN」その③――環境に対する識別をどう分かち合うか
ヨゼフ・アベイヤ(福岡教区司教、「ラウダ―ト・シ」デスク担当司教)×荒川千衣子(「ラウダ―ト・シ」デスクメンバー)×光延一郎(イエズス会司祭、上智大学神学部教授)
フォーラム
◆座談会 藤沢教会、「伝える部門」――過去を受け継ぎ、今を作り、未来へと開かれる 編集部
藤沢教会では40年前から信徒が中心になって入門講座を行っています。当初、「自分と向き合い、イエスと向き合い、共同体と向き合う」グリフィン講座で始められましたが、後に「聖書と祈り」が付け加えられました。多くの時間を分かち合いに使う、信徒中心の生き生きとした養成講座に学んでみましょう。
月間テーマ ユダヤ教、キリスト教とパレスチナ
◆キリスト教シオニズムの歴史を考える 早尾貴紀(東京経済大学教授)
シオニズムの起源はユダヤ教ではなく、キリスト教にあると筆者は述べます。十字軍を発端に宗教を理由に領土を侵略することが始まり、下って一九世紀ではさらにプロテスタントの一部にユダヤ人の王国を復活させることが救済の一段階となるという思想が流行、それに影響を受けたユダヤ人がシオニズム運動を起こし、現代に至ると論じています。
◆モーセ五書におけるシオニズムの起源 金井美彦(日本基督教団砧教会牧師。立教大学兼任講師)
申命記7章は、約束の地で異邦人を殲滅させる思想があると確かに読み取ることができてしまう個所です。ここを文字通り、原理主義的に解釈することは大変に危険であり、現在、ガザ地区で起きているジェノサイドと無関係ではないことを示します。
◆インタビュー パレスチナにおける援助の限界と役割 金子由佳(立教大学兼任講師。国際協力NGO職員)
「気持ちを言葉にしようとするたびに、叫びたくなります。瓦礫や石と入り混じった幼い子どもたちの遺体が目に焼き付いています」。この世の地獄と言われる現在のガザ地区についてのレポート。筆者の現地友人からの肉声を交え、戦慄なしには読むことができない、文字通り言葉を失う惨状が描かれています。
連 載
◆見失われた羊に寄りそって 5 見失った1匹が群れに戻るには 英 隆一朗(イエズス会司祭)
◆京・江戸・博多、そして巴里 38 旧統一教会に対する解散命令について 南野 森(憲法学者)
◆風よ! 炎よ! 私にことばを! 38 AIの時間と人間の時間 有村浩一(本誌企画委員)
◆旧約聖書のダメ男たち――ドキッ! それ私のこと? 5 アビメレク 北 博(聖書学者)
◆ペラギウス派と古代東方神学――具体的自由としての恩恵 5
補遺―初期キリスト教の発展要因(1) 山田 望(南山大学教授)
◆信仰を養う主日の福音 17 C年 復活節第3主日~復活節第6主日 雨宮 慧(東京教区司祭)
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語(続編) 第5回 「神殿」という住まい 高橋洋成(セム語〈ヘブライ語〉学者)
◆つうしん
noteによる記事購入↓

○月刊『福音宣教』トップページへ
●2026年 6月号 月間テーマ 全国の教会の現状(1)
特別連続座談会
◆日本カトリック司教団『見よ、それはきわめてよかった――総合的な(インテグラル)エコロジーへの招き』を読む 6 第三部「行動する ACT」その①――責任ある地球市民として神の愛をあかしする
ヨゼフ・アベイヤ(福岡教区司教、「ラウダ―ト・シ」デスク担当司教)×荒川千衣子(「ラウダ―ト・シ」デスクメンバー)×光延一郎(イエズス会司祭、上智大学神学部教授)
フォーラム
◆岩下壮一の青春(1) 岩下壮一を創ったもの――父・山本信次郎・ケーベル 加藤和哉(聖心女子大学教授)
岩下壮一は、深い学識と幅広い教養を持ち、若者や病者のために献身した実践家であり、明治以降の日本において最も卓越したカトリック司祭の1人です。未発表資料を読み解き、彼のこれまであまり知られていなかった側面が明らかにされていく、3回連載の第1回目です。
月間テーマ 全国の教会の現状(1)
◆社会は教会、小教区はその一部 松村繁彦(大阪高松教区司祭、札幌教区事務局長)
この50年で大きな変化を被っている札幌教区。高齢化と人的資源の減少により、筆者は11もの小教区の主任司祭を兼任。キリシタン時代にも似た状況下、長らく受け身であった信徒の役割を根本的に見直し、信徒が能動的に司祭と共同責任を担い、信徒使徒職を実行する以外に未来がないことが伝わってくる記事です。
◆長崎教区 教育現場の現状と使命 坂本久美子(純心聖母会会員、長崎純心大学学長)
長崎のミッションスクールの生徒は、信者であっても長らく教会には行っていない生徒が多いようだという現状報告がある中、先達によって培われたカトリック学校の使命、信仰教育と人格教育がますます重要であることが語られます。生涯をかけて「知恵のみちを歩み、人と世界に奉仕する」人を育てていく著者の真摯な姿勢が伝わってきます。
◆ここに教会があること――こだまする福音 大西勇史(広島教区司祭)
たとえ非常に小さな田舎の教会であっても、信徒の数は少なくとも、信仰の灯は優しく、温かいものです。傷ついた人をひきつけ、皆で助け合い、関わり合っていく姿、教会の原点の在り方を示す忘れがたい思い出を分かち合ってくださいました。
連 載
◆見失われた羊に寄りそって 6 障がいの2つのモデル 英 隆一朗(イエズス会司祭)
◆京・江戸・博多、そして巴里 39 教皇フランシスコ逝去 南野 森(憲法学者)
◆風よ! 炎よ! 私にことばを! 39 教皇フランシスコ後の懸念 伊能哲大(本誌企画委員)
◆旧約聖書のダメ男たち――ドキッ! それ私のこと? 6 サムソン 北 博(聖書学者)
◆ペラギウス派と古代東方神学――具体的自由としての恩恵 6
補遺―初期キリスト教の発展要因(2) 山田 望(南山大学教授)
◆信仰を養う主日の福音 18 C年 主の昇天~聖ペトロ 聖パウロ使徒 雨宮 慧(東京教区司祭)
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語(続編) 第6回 「風琴」という交響曲 高橋洋成(セム語〈ヘブライ語〉学者)
◆つうしん
noteによる記事購入↓

○月刊『福音宣教』トップページへ
●2025年 7月号 月間テーマ 教皇フランシスコの遺産
特別連続座談会
◆日本カトリック司教団『見よ、それはきわめてよかった――総合的な(インテグラル)エコロジーへの招き』を読む 7 第三部「行動する ACT」その②――ともに歩み、ともに識別する教会共同体へ
ヨゼフ・アベイヤ(福岡教区司教、「ラウダ―ト・シ」デスク担当司教)×荒川千衣子(「ラウダ―ト・シ」デスクメンバー)×光延一郎(イエズス会司祭、上智大学神学部教授)
月間テーマ 教皇フランシスコの遺産
◆教皇フランシスコの信仰 ホアン・アイダル (Juan Carlos Haidar●イエズス会会員。上智大学神学研究科委員長)
教皇フランシスコが残してくださったものでもっとも素晴らしいものは、彼の信仰だったと、若い頃から指導を受けてきた筆者は言います。彼が他人の悪口を言っているという話は聞いたことがないそうです。謙遜さと貧しさに貫かれた態度は、一生涯を通して貫かれていました。
◆神の民である教会を活かした教皇――フランシスコ教皇を偲んで デ・ルカ・レンゾ(De Luca Renzo●イエズス会会員。日本二十六聖人記念館館長)
教皇フランシスコに謁見した人は、どんな相手であろうと「自分だけに特別に関わってくださる」と思わせることが多かったそうです。一人ひとりの人間を大切にして向き合う態度は、神の民を育て、世界を大切にし、環境を大切する心と首尾一貫してつながっていました。
◆教皇フランシスコのイザヤ書に沿ったアピール――「アフリカから手を引け!」(上) カブンディ・オノレ(Kabundi Honore●淳心会会員。オリエンス宗教研究所所長)
教皇ブランシスコは2023年、コンゴ民主共和国(以下コンゴと略)の悲惨な状況に心を痛め、38年ぶりの教皇によるコンゴ訪問を決断。豊かな資源と人材を搾取する国際社会に向かって「コンゴから手を引け! アフリカから手を引け!」と激しい訴えを行いました。「主のしもべの歌」になぞらえ、国内に居ながらにして捕囚されている民の悲惨な現状を前に、世界の人々へ問いかけが迫ります。
◆教皇フランシスコに導かれて、新たな共同体、新たな自分 山野内公司+信徒の皆様(やまのうち・ひとし●サレジオ修道会会員)
教皇フランシスコが打ち出してきた指針を誠実に、また着実に実行してきた筆者が、共に歩みをともにしてきた信徒と、フランシスコの就任から逝去までの間の歩み、その間成長してきた教会の歩みを振り返ってくださいました。
連 載
◆見失われた羊に寄りそって 7 出向いていく牧者 英 隆一朗(イエズス会司祭)
◆京・江戸・博多、そして巴里 40 決戦の夏 南野 森(憲法学者)
◆風よ! 炎よ! 私にことばを! 40 教皇フランシスコとの思い出 西村桃子(本誌企画委員)
◆旧約聖書のダメ男たち――ドキッ! それ私のこと? 7 サウル 北 博(聖書学者)
◆ペラギウス派と古代東方神学――具体的自由としての恩恵 7
教会史的問題状況 山田 望(南山大学教授)
◆信仰を養う主日の福音 19 C年 年間第14主日~年間第17主日 雨宮 慧(東京教区司祭)
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語(続編) 第7回 「りんご」という工夫 高橋洋成(セム語〈ヘブライ語〉学者)
◆つうしん
noteによる記事購入↓

○月刊『福音宣教』トップページへ
●2025年 8・9月号 月間テーマ 教皇レオ14世の横顔
特別連続座談会
◆日本カトリック司教団『見よ、それはきわめてよかった――総合的な(インテグラル)エコロジーへの招き』を読む 最終回 第三部「行動する ACT」その③――「何倍も幸せになるためにやる」
ヨゼフ・アベイヤ(福岡教区司教、「ラウダ―ト・シ」デスク担当司教)×成井大介(新潟教区司教。「ラウダート・シ」責任司教)×伊藤幸史(新潟教区司祭。「信州風の家」代表)×荒川千衣子(さいたま教区信徒。「ラウダ―ト・シ」デスクメンバー)
◆岩下壮一の青春(2) 導かれるままに 加藤和哉(聖心女子大学教授)
◆教皇フランシスコのイザヤ書に沿ったアピール――「アフリカから手を引け!」(下) カブンディ・オノレ(淳心会会員。幣研究所所長)
月間テーマ 教皇レオ14世の横顔
◆教皇レオ14世の選出 菅原裕二 (イエズス会会員。教皇庁立グレゴリアン大学教会法学部名誉教授)
教皇レオ14世の人物像について総合的な視点で紹介されています。教会法の知識、米国出身でありながら南米での長い司牧経験、アウグスチノ会総長として、また司教、枢機卿として国際的な統治の経験、マルチリンガルであること、そしてカトリック教会初の社会教説を発表したレオ13世の後継者として、現代社会との対話を進めていくことが期待されます。
◆教皇レオ14世の誕生――聖アウグスチノの息子として 柴田弘之(聖アウグスチノ修道会会員。カトリック葛西教会主任司祭)
教皇を輩出することになったアウグスチノ会会員の立場から、その当初の驚きと、「ボブ」と呼ばれ親しまれたプレボスト総長時代の思い出や、そのころ手がけた難民や病者への実際の支援の数々のエピソードを交え、聖アウグスチノ修道会の精神、すなわち社会的・文化的違いを認め合い、一致する精神を実現する希望について綴っていただきました。
◆総長ロバート・プレボストから教皇レオ14世へ 今田昌樹(聖アウグスチノ修道会会員。聖マリア学院理事長)
プレボスト総長の時代に日本分管区長であった筆者の個人的な出会いの経験から、教皇の人となりを伺わせるエピソードの数々が紹介されています。控えめで地味に見えながらも実は本当はとても頼りになる、そういうボブ・プレボスト師の人柄についてお書きいただきました。
連 載
◆見失われた羊に寄りそって 8 2人のアメリカ人、2人の羊飼い 英 隆一朗(イエズス会司祭)
◆京・江戸・博多、そして巴里 41 ぬちぬ ちるがたん 南野 森(憲法学者)
◆風よ! 炎よ! 私にことばを! 41 パウロの言葉をたどる旅 萩原千加子(本誌企画委員)
◆旧約聖書のダメ男たち――ドキッ! それ私のこと? 8 ダビデ 北 博(聖書学者)
◆ペラギウス派と古代東方神学――具体的自由としての恩恵 8
幼児洗礼義務化への経緯――ペラギウス派排斥の教会史的前提 山田 望(南山大学教授)
◆信仰を養う主日の福音 20 C年 年間第18主日~年間第26主日 雨宮 慧(東京教区司祭)
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語(続編) 第8回 「雨」という実り 高橋洋成(セム語〈ヘブライ語〉学者)
◆つうしん
noteによる記事購入↓

○月刊『福音宣教』トップページへ
●2025年 10月号 月間テーマ 全国の教会の現状(2)
フォーラム
◆教会の使命とリーダーシップにおける女性の参加(1) カブンディ・オノレ(淳心会会員。幣研究所所長)
◆岩下壮一の青春(3) 20世紀のフランシスコ・ザビエル 加藤和哉(聖心女子大学教授)
世のメタファーを読む
◆森の護り手たちと森という護り手 濱田欧太郎(フランシスコ会士)
月間テーマ 全国の教会の現状(2)
◆「最前線」を生きる教会 谷脇慎太郎 (横浜教区司祭、同教区事務局長)
横浜教区事務局長による教区の現状についての率直なレポートです。そこに危機があり、対処すべき問題が山積している様子を、コロナ禍の最初の兆候であった2020年のダイヤモンド・プリンセス号での集団感染に譬えています。「生き残り」ではなく、「使命を生きる」ということが問われています。
◆フードパントリー「ぶどうの木とくでん」への歩み 三上一雄(北海道出身。東京教区信徒)
最初は4人の作業チームから始まった徳田教会のフードパントリー。今では大きく成長し、地域との連携の中でつながりを作り出しています。筆者は1980年代から東京・三谷で支援活動を続けており、徳田教会を設立したフロジャック神父の精神に共鳴、今につながっています。
◆埼玉から宮崎の教会へ 若山治憲(埼玉県出身。大分教区信徒、2014年、宮崎に移住)
埼玉から宮崎の教会へ移り住んだ筆者は、夫婦で地方の小さな素朴で優しい共同体の中に溶け込み、いつしか教会の重要な役割を果たすことに。そこから宮崎の諸教会との連携や、地域の不登校の子どもたちのフリースペース設立へと広がっていった経緯を振り返っていただきました。
連 載
◆見失われた羊に寄りそって 9 羊飼いのジレンマ 英 隆一朗(イエズス会司祭)
◆京・江戸・博多、そして巴里 42 猿がどうしたという話では 南野 森(憲法学者)
◆旧約聖書のダメ男たち――ドキッ! それ私のこと? 9 イエフ 北 博(聖書学者)
◆ペラギウス派と古代東方神学――具体的自由としての恩恵 9
ペラギウス派排斥に至る教会史的経緯 山田 望(南山大学教授)
◆信仰を養う主日の福音 21 C年 年間第27主日~年間第30主日 雨宮 慧(東京教区司祭)
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語(続編) 第9回 「土」という財産 高橋洋成(セム語〈ヘブライ語〉学者)
◆つうしん
○月刊『福音宣教』トップページへ
●2025年 11月号 月間テーマ ニケア公会議から1700年
フォーラム
◆第16回シノドスにおける変容(1) ジャン=クロード・オロリッシュ(ルクセンブルク大司教、枢機卿。第16回シノドス通常総会総書記)
通訳として若い頃から各シノドスに立ち会ってきた筆者(元上智大学副学長)による証言をお届けいたします。教皇フランシスコの時代、特に第16回シノドス通常総会がいかに大きな変容をし、今まさに教会が大きく開かれていく転機に差し掛かっていることを感じてみてください。
◆教会の使命とリーダーシップにおける女性の参加(2) カブンディ・オノレ(淳心会会員。幣研究所所長)
月間テーマ ニケア公会議から1700年
◆三位一体論形成時代における異端と現代におけるその意義 ハンス・ユーゲン・マルクス (神言修道会会員。前藤女子大学学長)
キリスト教会の中で多くの異端との闘いであったニケア公会議前後の時代、さまざまなな思潮がどのようにキリスト教の根幹となる三位一体論の形成に役割を果たしてきたか、簡潔に描かれています。
◆ニカイア信条の教理的な特色――三位一体論の形成 関川泰寛(大森めぐみ教会牧師。日本神学センター会長)
ニケア信条において、古代世界に一般的であった中期プラトン主義の神概念が聖書的な方向に明確に修正され、現代へと繋がる、創造と救済が受肉において具現化されるという神学の方向性が打ち立てられていきます。
◆もう一つの信条――使徒信条の成立と現代における意義 本城仰太(東京神学大学准教授・中渋谷教会牧師)
ニケア信条より古い使徒信条の成立の歴史を追い、広くプロテスタント、カトリックで共有されている使徒信条の現代的な意義について学べる内容となっています。
連 載
◆見失われた羊に寄りそって 10 一匹の孤独 英 隆一朗(イエズス会司祭)
◆京・江戸・博多、そして巴里 43 パリで祈る人々 南野 森(憲法学者)
◆旧約聖書のダメ男たち――ドキッ! それ私のこと? 10 ホセア 北 博(聖書学者)
◆ペラギウス派と古代東方神学――具体的自由としての恩恵 9
ペラギウス派排斥に至る教会史的経緯 山田 望(南山大学教授)
◆信仰を養う主日の福音 22 C年 死者の日~A年 待降節第1主日 雨宮 慧(東京教区司祭)
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語(続編) 第10回 「箱舟」という文化 高橋洋成(セム語〈ヘブライ語〉学者)
◆つうしん
○月刊『福音宣教』トップページへ
●2025年 12月号 月間テーマ 聖年を振り返って――青年の集い
フォーラム
◆第16回シノドスにおける変容(2) ジャン=クロード・オロリッシュ(ルクセンブルク大司教、枢機卿。第16回シノドス通常総会総書記)
◆現代の「神の民」に連なって(1)――基地の街横須賀で学び考えたこと 浜崎眞実(横浜教区司祭。沖縄教区派遣)
米軍基地に隣接の神奈川県横須賀の三笠教会で基地問題に長らく取り組んでこられた筆者による総括、第1回目。この地に派遣された召命を生き、教会外組織と連携しての運動、教会内でのフィリピンコミュニティなどとの協力と粘り強い抗議、交渉によって外国籍の人々の滞在権と住居を確保するエピソードなど、行政を動かした例を学ぶことができます。
月間テーマ 聖年を振り返って――青年の集い
バチカンで行われた聖年の「青年の祝祭」のレポートを3本お届けいたします。
◆祈るということ、伝えていくということ 古川舞乃 (福岡教区笹岡教会信徒)
思春期におけるカトリック教会への反発と嫌悪にも関わらず、司祭との出会いによって青年会に参加し、少しずつ変容していき、バチカンへの巡礼によって得た恵みと感動の手記。人生の中で大きな宝物を得たことが伝わってきます。
◆神の恵み、心が燃えたこと 秋元 惇(札幌教区小樽教会信徒)
巡礼のクライマックスである教皇ミサの前日、夜を徹しての友との語り合い、仲間たちとの親密な交流によって信仰に燃え上がる様子を率直に、また赤裸々に綴ってくださいました。涙に溢れる巡礼の新鮮な喜びを感じてみましょう。
◆「希望の巡礼者」として 村山美遊(東京教区高輪教会信徒)
ただ感動して巡礼を終えるのではなく、「自分の教会の場で何ができるか」を具体的に考え始め、合宿やネットワークミーティングの集いなどの教区を超えた交流へと開かれ、希望の巡礼者として歩み続けている様子に心打たれます。
連 載
◆見失われた羊に寄りそって 11 羊飼いのわな――共依存 英 隆一朗(イエズス会司祭)
◆京・江戸・博多、そして巴里 44 女性首相の誕生 南野 森(憲法学者)
◆風よ! 炎よ! 私にことばを! 42 シノドス流の教会を実現するには? 有村浩一(本誌企画委員)
◆旧約聖書のダメ男たち――ドキッ! それ私のこと? 最終回 アダム 北 博(聖書学者)
◆ペラギウス派と古代東方神学――具体的自由としての恩恵 11 研究史概観 山田 望(南山大学教授)
◆主日の福音を通してみ言葉を生きる 1 A年 待降節第2主日~聖家族 山下 敦(大分教区司祭)
◆ヘブライの言葉、イスラエルの物語(続編) 第11回 「エベル」という理解 高橋洋成(セム語〈ヘブライ語〉学者)
◆つうしん
○月刊『福音宣教』トップページへ
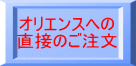
○富士山マガジンサービスからご注文